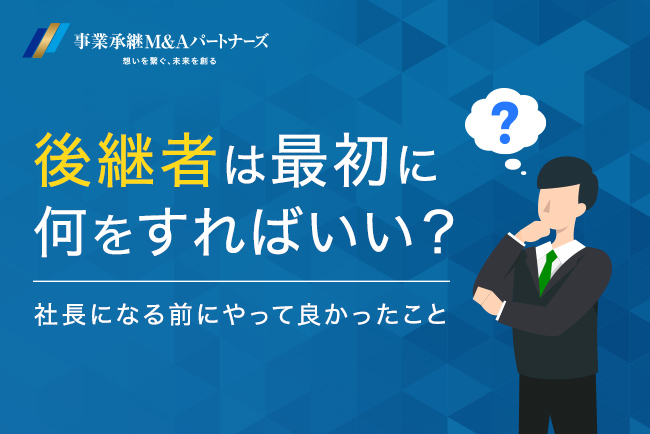亡くなった方の遺産が一定額以上の場合、遺産を相続した相続人は相続税の納税義務が生じますが、納税額を計算する時に忘れてはいけないのが基礎控除です。
誤った金額で申告してしまわないためにも、きちんとその仕組みを理解しておかなければいけません。
しかし、控除額の計算方法は決して単純ではなく、初めての方が正確に計算するのは一苦労です。
本記事では基礎控除を始め、相続人が活用できる控除や特例について詳しく解説していくので、よければ参考にしてみてください。
相続税の基礎控除とは

そもそも相続税とは、故人から相続する遺産に対して発生する税金のことです。
相続する遺産の総額が大きければ大きいほど、相続税も高くなりますが、相続税には基礎控除という誰に対しても適用される制度があります。
遺産から基礎控除を差し引いた金額に対してのみ相続税が発生します。
裏を返すと、基礎控除を差し引いた時点での遺産の評価額がゼロであれば、相続税は発生しないということになります。
相続税は相続人自身が申告する
相続税に関してまず理解しておかなければいけないことは、相続税は遺産を受け取る相続人自身が申告しなければいけないということです。
一般的には相続人全員が連名で提出することが多いですが、専門知識なしで控除などを正確に計算するのは難しいでしょう。
また、相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10カ月以内であり、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税といったペナルティが科されます。
誤りなく確実に申告するには、税理士に協力を依頼するのが望ましいでしょう。
相続税の1人あたりの基礎控除
基礎控除の具体的な金額について解説していきます。
基本的な計算式は「3,000万円 + (法定相続人の人数 × 600万円)」となっています。
つまり、相続人が1人だけであれば「3,000万円 +( 1人 × 600万円)」で3,600万円。
人数が増える場合、1人につきさらに600万円が加算されていくだけなので、基礎控除だけであればそこまで複雑な計算ではありません。
尚、平成27年の税制改正以前の基礎控除は「5,000万円 + (法定相続人の人数 × 1,000万円)」だったため、改正によって40%も減額されたことになります。
遺産の種類・内訳

ちなみに遺産についてですが、その評価額は単純に現金や不動産だけで決まるわけではありません。
大きく分けて以下の5種類があり、その合計が最終的な遺産の評価額ということになります。
- 積極財産
- 消極財産
- みなし相続財産
- 非課税財産
- 贈与財産
積極財産
- 現金
- 不動産
- 動産
- 金融資産
上記のように、わかりやすく金銭的な価値を有するものを「積極財産」、あるいは「プラスの財産」と呼びます。
他にも様々なものがこの積極財産に含まれる可能性がありますが、申告に漏れがあると過少申告加算税が科される恐れがあるため、特に注意が必要な項目です。
消極財産
- 借入金
- 手形債務
- 買掛金
- 未払いの税金
- 葬式費用(初七日・四十九日に要した費用、香典返し等一定のものを除く)
積極財産とは反対に、上記のような被相続人が抱えていた負債などを「消極財産」、または「マイナスの財産」と呼びます。
これらも相続人が引き継ぐことになりますが、中には身内も把握していない消極財産が存在している可能性もあるため、早急に専門家に調査を依頼した方が良いでしょう。
みなし相続財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
被相続人が所有していたわけではないものの、本人の死亡をきっかけとして受け取る財産を「みなし相続財産」と呼びます。
ただ、上記の2つを含め、みなし相続財産には非課税枠が設定されているものもあり、全額が課税対象になるわけではありません。
非課税財産
- 仏具・仏壇
- 墓地・墓石
これらの財産は「非課税財産」として扱われ、文字通り課税対象にはなりません。
ここに挙げているもの以外にもいくつか例はありますが、金仏具のように骨董品としての価値がある場合は課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
贈与財産
相続開始日から遡り、一定期間内に被相続人から相続人への贈与があった場合には、相続税の計算上、相続財産に加算されて相続税が計算されます。
尚、令和5年以前の贈与であれば、相続開始日から3年以内の贈与が対象となっていましたが、令和5年度の税制改正により、令和6年以降の贈与に関しては相続開始日から7年以内が対象となります。
贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられており、それに収まる範囲であれば贈与税は非課税となりますが、上記の期間内に贈与された場合には相続税の対象になります。
相続税の対象となる法定相続人

遺産を受け取り、相続税を支払わなければいけない可能性がある法定相続人について解説していきます。
まず、必ず法定相続人に数えられるのは故人の妻、もしくは夫である配偶者です。
事実婚である内縁の配偶者や、既に離婚している元配偶者は法定相続人として認められません。
そして被相続人の血縁者も法定相続人に数えられますが、以下の表のように相続順位が定められています。
| 相続順位 | 法定相続人 |
| 第1順位 | 直系卑属となる子(亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 直系尊属となる父母(死亡している場合は祖父母) |
| 第3順位 | 傍系血族となる兄弟・姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
配偶者の有無による相続分の違い
次に各相続人が相続できる遺産の割合を示す、相続分について解説しますが、配偶者とその他の法定相続人が受け取る相続分は以下のようになります。
| 相続順位 | 法定相続人:相続分 | |
| 子どもがいる場合 (第1順位) |
配偶者:1/2 | 子ども:1/2 (全員で等分) |
| 子どもがおらず、父母がいる場合 (第2順位) |
配偶者:2/3 | 父母:1/3 (全員で等分) |
| 子ども、父母がおらず、兄弟・姉妹が要る場合 (第3順位) |
配偶者:3/4 | 兄弟・姉妹:1/4 (全員で等分) |
このように相続順位に応じて相続分は異なります。
また、配偶者以外の法定相続人が複数人いる場合は、定められた相続分を全員で等分することになります。
尚、配偶者がいない場合は遺産の全額を、優先順位の高い法定相続人で等分します。例えば、配偶者がおらず、子どもが3人いる場合は遺産を3等分して相続することになります。
1人あたりの相続税を遺産総額・家族構成別に紹介

基礎控除の計算方法や相続分を理解しても、実際にどれほどの相続税がかかるのか、イメージすることは難しいでしょう。
相続税は、基礎控除額を差引いた課税対象額を、各相続人の法定相続分に按分した金額に以下の税率を乗じて計算した金額の合計額となります。
なお、超過累進課税を用いて計算されるため、課税額を複数の区分に分けて、区分ごとに税率を計算する仕組みです。
| 相続税の課税対象額 | 税率 |
| 1,000万円まで | 10% |
| 3,000万円まで | 15% |
| 5,000万円まで | 20% |
| 1億円まで | 30% |
| 2億円まで | 40% |
| 3億円まで | 45% |
| 6億円まで | 50% |
| 6億円超 | 55% |
遺産総額と家族構成別に解説するので、良ければ参考にしてみてください。
相続人が配偶者と子どもの場合
| 遺産総額 | 配偶者・子ども1人 | 配偶者・子ども2人 | 配偶者・子ども3人 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | – |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
| 3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
| 4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 |
| 20億円 | 4億6,645万円 | 4億3,440万円 | 4億1,182万円 |
| 30億円 | 7億4,145万円 | 7億380万円 | 6億7,432万円 |
相続人が子どものみの場合
| 遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 |
| 4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
| 20億円 | 10億820万円 | 9億3,290万円 | 8億5,760万円 |
| 30億円 | 15億5,820万円 | 14億8,290万円 | 14億760万円 |
相続税の基礎控除以外の控除一覧

基礎控除は遺産総額から控除されますが、以下に紹介している控除制度は、相続税額から直接控除される制度です。
どれも重要なものばかりなので、それぞれの内容を確認しておきましょう。
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
贈与税額控除
前述したように、相続開始日から遡って3年以内(令和6年以降であれば7年以内)に贈与された財産は、相続財産として再計算されます。
しかし、既に贈与税を支払っていた場合、相続税と合わせて二重に納税してしまうことになってしまうため、それを打ち消す制度として「贈与税額控除」が設けられています。
事前に支払っていた贈与税が相続税を上回っていることも考えられますが、その場合相続税はゼロになるものの、差額分の贈与税が還付されることはありません。
配偶者控除
配偶者にとって最重要といっても過言ではないのが、配偶者控除です。
正式名称は「配偶者の税額軽減」といいますが、配偶者が相続する遺産に対して、1億6,000万円、もしくは法定相続分のいずれか高い方が非課税になります。
例えば、親子3人の家族構成で夫が亡くなってしまい、遺産が1億円である場合、法定相続分に沿って考えれば、配偶者である妻と子どもが5,000万円ずつ相続することになります。
その場合、配偶者控除によって妻は非課税ですが、子どもには相応の相続税が発生します。
ただし、配偶者控除によって1億6,000万円までが非課税になるため、もし妻が全額の1億円を相続すると、本来子どもが支払うはずだった相続税も発生しないということになります。
あくまでシンプルな例であり、必ずしもこのような手法が最適とも限りませんが、配偶者控除は上手く活用することで大きな節税効果を得られる可能性があります。
未成年者控除
配偶者控除と同じように、未成年の相続人をサポートする「未成年者控除(未成年の税額控除)」という制度もあります。
- 18歳未満であること
- 法定相続人であること
- 国内に住所があること(一定の要件を満たす国外居住者を含む)
上記3つの要件を満たしている場合のみ活用することができます。
控除額は相続開始日の年齢から、18歳になるまでの年数×10万円。例えば、10歳の子どもが活用する場合は80万円が控除されることになります。
尚、18歳までの年数を計算する際に1年未満は切り上げになるため、10年11ヶ月の子どもでも控除額は80万円になります。
もし未成年者控除額が相続税を上回る場合、余った差額分はその未成年者の扶養義務者である他の相続人の相続税から控除されます。
障害者控除
「障害者控除」は以下の要件を満たす相続人に適用される控除制度です。
- 障害者であること
- 85歳未満であること
- 法定相続人であること
- 国内に住所があること
控除額は一般障害者か特別障害者で異なり、一般障害者の場合は相続開始日の年齢から、85歳になるまでの年数×10万円、特別障害者の場合は同様の年数×20万円となっています。
ちなみに、未成年者控除と同様に、障害者控除の額が相続税を上回った場合も、その差額分は扶養義務者である相続人に適用されます。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した際に適用されるのが「相次相続控除」です。
例えば、祖父が亡くなってから10年以内に父親が亡くなった場合に適用され、その父親の相続人に課される相続税から既に父親が納税した相続税の一部が控除されます。
- 法定相続人であること
- 相続開始前10年以内に被相続人が財産を相続していること
- 相続開始前10年以内に被相続人が相続した財産に対して、相続税が課税されたこと
要件は上記の通りです。
1度目の相続を一次相続、2度目の相続を二次相続と呼び、その間隔が短いほど控除額も大きくなります。
外国税額控除
- 国外の財産を取得した
- 現地の国の法令により、相続税に相当する税金が課された
上記を満たした場合に適用されるのが、外国税額控除です。
現地の相続税(あるいはそれに相当する税)の税率によって控除額は異なりますが、基本的にはそれと同程度が差し引かれます。
相続税の特例一覧
控除とは異なりますが、相続財産を減額できたり、相続した財産によっては納税猶予の適用が可能となる特例もあります。
これらも遺産を相続する際は重要になってくるので、合わせて把握しておいてください。
- 小規模宅地等の特例
- 納税猶予の特例
小規模宅地等の特例
遺産には現金の他に不動産なども含まれますが、もし遺産の大部分が土地などの不動産である場合、現金化が難しく、納税できない可能性があります。
その土地を生活の拠点としており、どうしても手放せないということもあり得ますが、そのような場合の対策として設けられているのが「小規模宅地等の特例」です。
免税率は土地の用途や面積によって異なり、最大で80%減額されます。
納税猶予の特例
「納税猶予の特例」は、相続財産が農地、非上場株式、個人の事業用資産、医療法人の持分の場合に適用される特例です。
例えば、農地は面積が広大であることが多く、相続税も高額になる傾向があります。
納税が難しいという理由で相続を放棄されてしまうと、農業者不足を助長することにもなりかねないため、その対策として農地も納税猶予の特例が適用されます。
猶予といったものの、本来の申告期限から20年経過した時点で納税は免税されます。
会社の後継者が知っておくべき事業承継税制

最後に、相続によって会社を引き継ぐことになった後継者の方に向けて、事業承継税制について解説していきます。
事業承継税制の概要
ここまで解説してきたように、会社を引き継ぐ際も相応の相続税や贈与税が発生します。
納税額が高額になることも珍しくなく、後継者に十分な支払能力がないと、事業承継そのものが難しくなるでしょう。
事業承継税制はそういった金銭的な要因が事業承継を妨げている問題を解消するために設けられた制度で、後継者に課せられる税金において、納税猶予を受けることができます。
猶予期間中は定期的に届出書を提出し続ける必要がありますが、最終的には相続税の全額、あるいは一部が減免されます。
事業承継税制の一般措置と特例措置
事業承継税制には一般措置と特例措置があり、特例措置は平成30年から令和9年までの時限措置となっています。
細かい相違点はいくつもありますが、特例措置の大きなメリットは相続税の対象となる株式が2/3から全株式になり、納税猶予割合も相続・贈与ともに100%になったということです。
加えて、事業承継税制の最大のハードルである雇用維持の要件が緩和され、活用しやすくなったといえるでしょう。
事業承継税制の注意点
事業承継税制は、事業承継にかかる贈与税もしくは相続税が猶予・免除されるため、大きな恩恵を受けられますが、その分手続きは複雑です。
申請時はもちろん、最終的な贈与税・相続税の免除に至るまでに何種類もの書類を提出し続ける必要があり、専門家の協力も欠かせません。
加えて取消事由がいくつもあり、いずれかに該当してしまうと本来の税金が課せられるだけでなく、猶予分の利子税まで支払わなくてはいけなくなるケースもあります。
控除を活用して適切な節税対策を
莫大な税金がかかり得る相続においては、有効な制度をフルに活用し、適切な節税対策を講じる必要があります。
今回紹介した基礎控除を始め、相続人の属性によって様々な控除や特例があるため、積極的にご検討ください。
ただし、具体的にどのような節税対策を取っていくべきか、ご自身で判断することは極めて難しいでしょう。
まずは専門家に相談し、そのシチュエーションに沿ったプランを提案してもらいましょう。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。