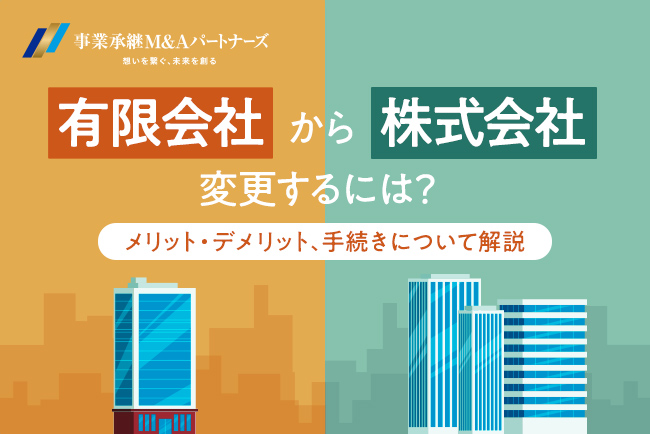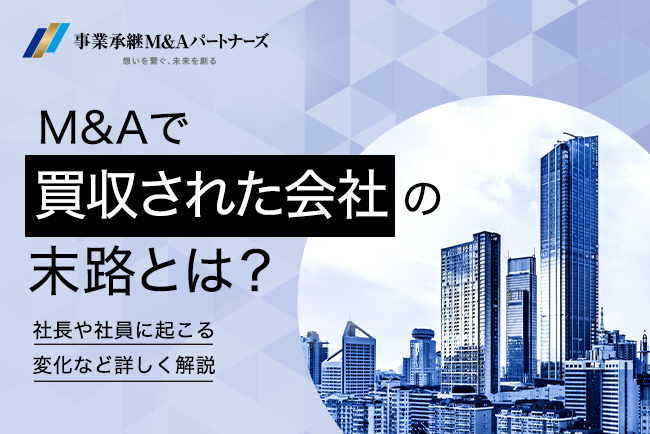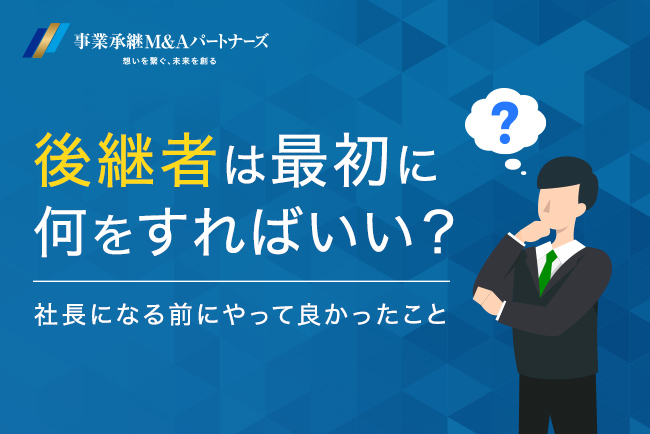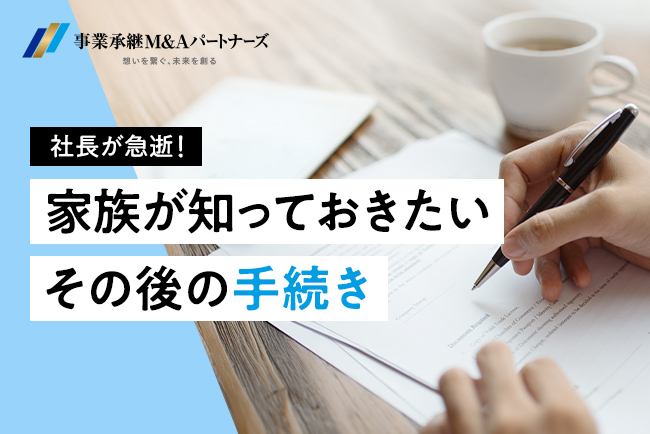相続対策や事業継承への準備のために、相続時精算課税制度の活用を考えている方は多いのではないでしょうか。
この制度は、贈与にかかる税金を抑えたり、資金を速やかに渡すために有効です。
しかし、場合によっては他の制度のほうが目的に合っている可能性があるため、慎重に選択する必要があります。
制度の内容と利用するメリットなどをしっかり把握し、適切に利用しましょう。
相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、生前贈与を行った場合、贈与にかかる贈与税が2,500万円まで非課税になるという制度です。
また、2,500万円までであれば何度でも非課税で贈与でき、上限を超えた分に関しては、税率20%の計算で納税が必要です。
ただし、これを選択すると、暦年課税に戻せない、また相続税の対象になることがある点には注意しなければなりません。
財産を渡す人が生前に贈与の税制度を利用して資産を譲った場合、その人が亡くなった後に、資産を受け取った側の相続財産の合計によっては、遺産にかかる税金が発生することがあります。
相続時精算課税制度の適用条件

相続時精算課税制度は、無条件で誰もが利用できる制度ではなく、適用に当たっては特定の条件を満たさなければなりません。
まずは、対象になる人や財産を確認しておきましょう。
利用できる人の条件
贈与を行う側(渡す人)は、その年の1月1日時点で60歳以上であることが要件となっており、加えて両親や祖父母など、受け取る人から見て直系尊属であることが必要とされています。
また、贈与を受ける側(もらう人)は、贈与が行われる年の1月1日時点で18歳以上であることが求められ、かつ、贈与者の子や孫といった直系卑属であることが条件です。
なお、2022年3月31日以前の贈与に関しては、適用対象年齢が20歳以上になっています。
厳格な条件が設定されている理由は、単なる節税目的の利用を防ぎ、世代間の財産移転の円滑化を促進するためです。
相続時精算課税の適用を検討する際には、将来的な資産の分配や税負担を考慮し、適切な計画を立てることが重要になります。
対象になる財産
相続時精算課税の適用対象となる財産には、とくに制限は設けられていません。現金、不動産、株式など、あらゆる種類の財産が対象になります。
前述のとおり贈与の回数や金額にも制限はなく、累計で2,500万円までの特別控除が適用されるのが特徴です。
また、事業継承税制との併用も可能で、非上場株式などの贈与では、納税猶予の取り消しにあたって制度を選択した時点の課税額が低くなります。
ただし、併用には事業継承税制、相続時精算課税制それぞれの条件を満たさなければなりません。
適用の手続きと必要書類
この制度を利用するためには、贈与税の申告期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日)に、所轄の税務署に贈与税の申告書を提出します。
その際、以下の書類が必要です。
- 受贈者の戸籍謄本または抄本:贈与を受ける人の氏名、生年月日、そして贈与者との続柄を証明するため
- 相続時精算課税選択届出書:贈与者と受贈者が異なる場合はその都度提出
戸籍謄本や抄本は、本籍を置く市区町村の役場窓口のほか、郵送で取得できます。また、コンビニ交付を利用できる場合もあるため、各役場のホームページなどで確認しましょう。
届出書の提出は、税務署窓口、郵送のほか、e-taxでも行えますが、書類の作成が不安な場合は専門家に依頼するのも一案です。
相続発生時の対応
贈与者が亡くなり相続が発生した場合、これまでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、相続財産として計上し、相続税の申告対象になります。
相続税の申告期限は、贈与者の死亡日または相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
この際、過去に相続時精算課税制度に基づき支払った贈与税額については、算出された相続税額から控除することが可能です。
また、相続財産の評価方法や税額控除の適用条件によっては、相続税の負担が変わる可能性があります。そのため、相続発生後はできるだけ早めに税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
相続時精算課税制度の計算方法

生前贈与において、相続時精算課税制度を用いた際の計算方法を確認していきましょう。仕組みを理解しておくことで、より制度を活用しやすくなります。
2,500万円の特別控除の仕組み
この制度では、贈与される財産2,500万円までが非課税扱いになります。
この特別控除額は資産を渡す人ごとに設定されており、複数の贈与を受ける場合、それぞれの贈与者ごとに2,500万円の控除枠が適用されます。
たとえば、父親から3,000万円、母親からも3,000万円の贈与を受けた場合、あわせて5,000万円までは贈与税がかかりません。
しかし、資産の提供者が亡くなった際には、控除額を差し引いた後の金額が相続財産に加算され、課税対象となる可能性があります。
超過分にかかる税率の計算例
贈与税にかかる相続時精算課税制度を利用した場合、累計で受け取った財産の合計が2,500万円を超えると、それを超えた部分に対して一律20%の税率が適用される仕組みになっています。
たとえば、全部で3,000万円の財産を受け取った場合、そのうち2,500万円を超えた500万円に対し、20%の税金が発生します。
【計算の具体例】
超過額の計算:3,000万円 – 2,500万円 = 500万円
適用される税額:500万円 × 20% = 100万円
年間ごとに課税される一般的な贈与税制度(暦年課税)と比べると、適用される税率が低く設定されているため、贈与税の負担を抑えることが可能です。
そのため、一定額以上の財産を計画的に移転したい場合には、有効な選択肢になるでしょう。
さらに、この税制を活用することで、将来的な相続時の税負担を軽減する効果も期待できます。
相続時の税額の計算方法
相続時精算課税制度を適用した場合、贈与者が亡くなった際には、これまでの累計贈与額(特別控除の2,500万円を含む)を相続財産に加算して遺産にかかる税を計算します。
たとえば、贈与者から生前に累計3,000万円の贈与を受け、相続時に5,000万円を受け取った場合、課税対象になるのは8,000万円です。
この8,000万円に対して相続税が計算されますが、贈与時に納めている贈与税に関しては、相続税から控除されます。
【前述の例により控除される贈与税】
贈与税額:超過分500万円 × 20% = 100万円
特定の贈与制度の適用には、贈与税の申告や相続税の計算などの複雑な手続きが伴うため、検討する際には税理士などの専門家に相談すると安心です。
相続時精算課税と暦年課税
ここでは、贈与時に選べる2つの制度の違いについて解説していきます。
条件や控除額などに違いがあるため、確認しておきましょう。
理解を深めることで、贈与にあたってどちらを選ぶべきか判断しやすくなります。
それぞれの制度の違い
それぞれの制度の違いは、主に下表のとおりです。
| 比較項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
| 贈与できる人の条件 | 受け取る側の親や祖父母にあたる満60歳以上の人 | なし |
| 贈与を受ける人の条件 | 贈与者の子や孫で18歳以上の人(2022年3月31日以前の贈与は20歳以上) | なし |
| 控除 | 2,500万円までの特別控除(渡す人ごと)+年間110万円の基礎控除(もらう人ごと) | 年間110万円の基礎控除(もらう人ごと) |
| 控除超過分の課税 | 固定税率20% | 超過累進課税(最大55%) |
| 手続き | 必要 | 不要 |
| 贈与税の申告 | 年間110万円以下の場合は不要 | |
| 贈与者が亡くなった際の相続税 | 年間110万円の基礎控除を超えた金額は、贈与時点の評価額で相続財産に加算される | 相続開始前7年間の贈与は相続財産に含まれる※最初の4年間は最大100万円まで対象外 |
どちらを選ぶべき?
これらの制度の選択は、贈与の目的や財産の状況、将来的な相続計画によって異なります。
どちらを選ぶかは、単純に贈与額のみで決まるものではなく、相続までの期間などさまざま要素を加味しなければなりません。
たとえば、最終的な贈与額が少なく、相続までの期間が短いなら相続時精算課税が、一方、累計額が多く贈与期間が10年を超えるような場合には、暦年課税のほうが有利になる可能性があります。
また、贈与者の年齢や健康状態も考慮する必要があり、たとえば資産を譲る人の余命が7年以内と予想されるようなケースでは、相続時精算課税のほうが有利になるかもしれません。
これはあくまでも一例であり、実際には個々の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが重要になります。
相続時精算課税制度で得られるメリット

資産を計画的に次世代へ移転したいと考える場合、相続時精算課税制度は有効な選択肢の一つになります。ここでは、制度を利用した贈与で得られるメリットを3つ解説します。
まとまった財産を早く渡せる
この制度を活用することで、子や孫といった次世代の後継者に対しての生前贈与がスムーズに行えます。
教育資金や住宅取得資金といった大きな支出が必要なタイミングで、計画的にまとまった資金を提供することが可能です。
大学進学やマイホームの購入など、一時的に多額の資金が必要になる場面では、大きな助けになるでしょう。
さらに、2,500万円までは贈与税の対象にならないため、必要に応じて資産を柔軟に移転できるのがこの制度の大きなメリットです。
また、財産を渡す側にとっても、将来的な相続税の負担を軽減する手段として活用できるため、長期的な資産管理の一環として有効です。
贈与税の負担を軽減できる
贈与された総額が2,500万円を超えた場合には、一律20%の税率が適用されます。
仮に超過額が500万円なら100万円で、1000万円であれば200万円です。
暦年贈与の場合は超過累進課税のため、年110万円を超えた額によって、10~55%の税率がかかります。
たとえば、5,000万円の財産を贈与するときに暦年課税制度を用いた場合は、およそ2,500万円の贈与税がかかることになります。
しかし、これが相続時精算課税であれば500万円ほどで済むため、一時的な税負担の軽減に効果的です。
このように、多額の贈与を行う際に、贈与税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
将来の相続対策になる可能性がある
相続時精算課税制度を活用して、不動産や土地、株式といった「将来的に価値が上昇する可能性のある財産」を早期に贈与すれば、相続時の課税評価額を抑えることができます。
これは贈与時の評価額で加算されるため、値上がり益に対する税負担の軽減になる可能性があります。
ただし、逆に譲り受けた資産の価値が下がった場合には、負担が大きくなるため注意が必要です。
また、生前に財産を分割して贈与することで、相続時の財産総額を把握しやすくなり、相続税の計画的な対策が可能になります。
とくに、複数の子供がいる場合は、平等に財産を分配する手段として有効です。
【相続時精算課税制度】デメリットと注意点

相続時精算課税制度を検討する際は、後悔しないよう、そのデメリットを知っておくことが大切です。
注意点もあわせて確認しておきましょう。
一度選択すると暦年課税には戻せない
相続時精算課税制度を一度選択すると、以後の贈与にはすべてこの制度が適用されるので、暦年課税制度には二度と戻せません。
たとえ選択後に、「暦年課税のほうが贈与に都合がいい」と思ったとしても、改めて選択し直すことは不可能です。
少額で年間の基礎控除額を超えないような贈与の場合は、初めから暦年課税を検討するとよいでしょう。
ただし、「父→長男は相続時精算課税」、「父→長女は暦年贈与」のように、贈与者と受贈者の組み合わせが異なる場合には、一方が暦年課税を選ぶことは可能です。
課税制度を選ぶ際は、それぞれのメリット・デメリットを十分に検討したうえで決める必要があります。
相続時に税金が発生するリスクがある
この制度では、贈与した財産の価値が相続時に相続財産に合算され、相続税の課税対象となります。
そのため、贈与の段階では納税額が少なくなったとしても、相続時に相続税が発生し、トータルでの税負担が増加するリスクがあります。
贈与税の負担がないことばかりに気を取られないようにしましょう。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の納税義務が生じる点に注意が必要です。
小規模宅地等の特例が対象外になる
小規模宅地等の特例を受けると、一定の条件下において相続税評価額が最大80%減額されます。
土地の評価額が低くなれば、おのずと納める税金も安くなります。
しかし、この特例を適用できるのは相続した場合に限られており、相続時精算課税制度を用いて贈与された土地には残念ながら適用されません。
そのため、土地の贈与に対して選択を間違うと、期待する節税効果が得られない可能性があります。
相続時精算課税が向いているケース

制度を活用するにあたって、適切なケースを把握しておくことは重要です。贈与の目的を明確にし、のちのち困らないように適用するかどうかを検討しましょう。
生前贈与で資産移転を計画したい
贈与における税制を活用することで、資金の移転がスムーズに行えるため、次のようにある程度の額を生前贈与したい場合に適しています。
- 生前にまとまった資産を子や孫に渡したい
- 教育資金や結婚資金など、必要な資金を適切なタイミングで贈与したい
- 経営者の生前から段階的に事業継承を進めたい
ただし、移転した資金は、相続が発生したときに相続財産に加算されるため、総合的な税負担を考慮することが重要です。
相続トラブルをなくしたい
相続トラブルは、大富豪の家でのみ起こるものではありません。
資産が数千万円だとしても遺族がもめるケースは多いです。
相続時精算課税は、相続によるさまざまなトラブルを防止するためにも有効です。
たとえば、後継者を決めずに経営者が亡くなった場合、意図しない人物が後継者になったり、家族が会社の相続で揉めたりしかねません。
その点、生前に株式や事業用資産を後継者へ贈与しておけば、このようなトラブルを避けられるでしょう。
ただし、贈与税を節約するために土地を共有させる、贈与をほかの家族に隠しておくといったことをすると、かえってトラブルを招きかねないため注意してください。
住宅取得資金を援助したい
子や孫が住宅を取得する際の資金援助をしたい場合、相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度を併用することで、最大3,610万円までの贈与が非課税になります。
適用するためには住宅の要件を満たす必要がありますが、制度の組み合わせにより、住宅購入資金の大部分を非課税で贈与することが可能です。
また、条件によっては贈与する側が60歳未満でも適用されるため、最適なタイミングで援助できます。
相続時精算課税制度の利用は専門家に相談
相続時精算課税制度の活用は、贈与時の税負担を軽減するほか、相続対策になるといったメリットがあります。
まとまった資産を譲りたい場合や、早期に移転させたい場合には有効な手段といえるでしょう。
しかし、手続きを忘れたり適切な制度を選べなかったりすると、メリットを最大限に享受できません。
また、結果的に期待した効果が得られない、トラブルのきっかけになるといったことも考えられるため、適用にあたっては慎重に検討する必要があります。
制度を利用するべきかどうかの判断や、書類の作成などは、税制の専門家に相談すると安心です。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。