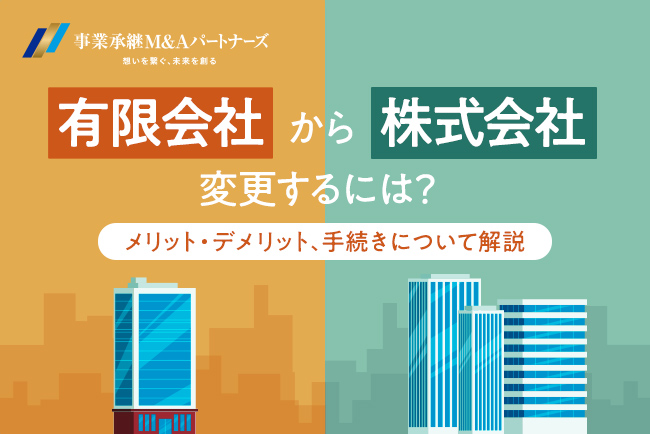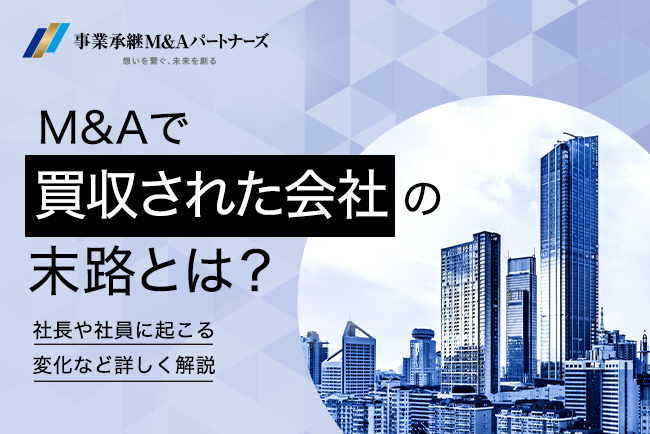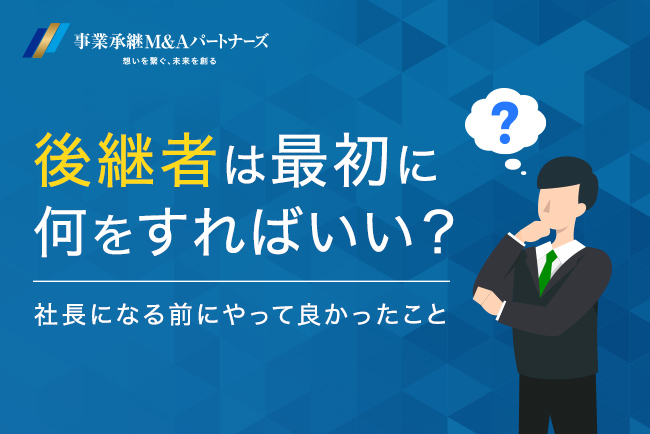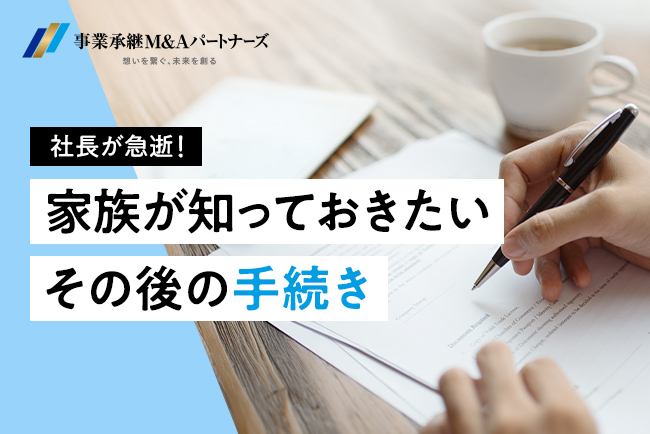企業が他社の株式を一定割合以上保有すると、その会社は「持分法適用会社」となります。
持分法適用会社は、親会社の連結決算において特別な会計処理が適用されるため、財務諸表にも影響を与えます。
特にM&Aや企業提携の場面では、この概念を正しく理解することが重要です。
本記事では、持分法適用会社の定義や連結子会社との違い、メリットなどについて詳しく解説します。
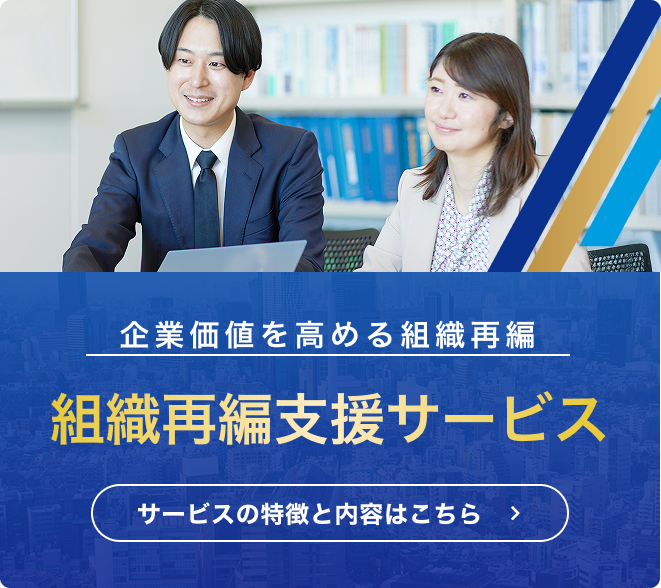
持分法とは?

持分法とは、企業が関連会社の株式を一定割合以上保有している場合に、その企業の財務状況や業績を投資企業の決算に反映する会計処理です。
原則として、議決権の20~50%を保有し、経営に重要な影響を及ぼす場合に適用されます。
持分法は、単なる投資とは異なり、関連会社の財務状況を適切に反映することで、投資企業の実態に即した財務報告を行うことを目的としています。
関連会社の純利益や純資産の変動が、投資企業の財務諸表にも影響を与えるため、グループ全体の経営状況をより正確に把握することが可能です。
そして、持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことを、持分法適用会社といいます。
持分法の適用範囲
持分法の適用範囲は、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)では異なるため、注意しなければなりません。
ここでは、日本の会計基準に基づいて持分法の適用範囲を解説します。
関連会社
関連会社とは、企業が一定の議決権を保有し、経営に重要な影響を与えると判断される会社のことです。
通常、議決権の20~50%を保有している場合に「関連会社」として扱われ、持分法の適用対象となります。
ただし、取締役の派遣や経営方針決定への関与、資金や技術の提供などを通じて実質的に影響力を持つ場合には、議決権比率が20%未満でも関連会社に該当する場合があります。
非連結子会社
非連結子会社とは、親会社の立場からして重要性が低かったり、支配が一時的なものであったりする場合において、連結決算の対象から除いた子会社のことです。
通常、非連結子会社は連結決算の対象から外すことは可能ですが、親会社の議決権比率が20~50%の場合は、持分法適用会社となるため連結財務諸表で持分法が適用されます。
持分法適用会社と連結子会社の違い

企業が他社の株式を保有すると、経営への関与度合いによって「持分法適用会社」または「連結子会社」として扱われます。
持分法適用会社は、議決権の20~50%を保有し、経営に「重要な影響を与える」企業です。
財務処理では「持分法」を適用し、関連会社の利益や資産の変動を、持分割合に応じて投資企業の決算に反映します。
ただし、連結財務諸表には統合されません。
連結子会社は、議決権の50%超を保有し、親会社が経営をコントロールできる企業です。
財務処理では、子会社の資産・負債・収益・費用をすべて親会社の財務諸表に統合します。
つまり、持分法適用会社は影響を与える立場、連結子会社は実質的に経営を支配する立場という違いがあります。
財務処理の影響も大きく異なるため、企業の財務分析では両者の違いを正しく理解することが重要です。
| 項目 | 持分法適用会社 | 連結子会社 |
| 支配力の強さ | 重要な影響力を持つが支配はない | 支配権を持つ |
| 保有議決権の割合 | 20~50% | 50%超 |
| 財務諸表の扱い | 持分法を適用(投資額と利益を一部反映) | 親会社の連結諸表に完全統合 |
持分法適用会社の確認方法
対象会社が持分法適用会社かどうかを確認する方法には、以下の3つがあります。
- 連結財務諸表の「注記事項」を確認する
- 有価証券報告書の「関係会社の状況」を確認する
- 有価証券報告書の「注記事項」を確認する
連結財務諸表は、グループ全体の財務状況を表す重要な書類で、その中の「注記事項」に持分法適用会社について記載されていることが一般的です。
連結財務諸表の注記事項に記載がない場合は、有価証券報告書の「関係会社の状況」または「注記事項」に記載されているでしょう。
持分法のメリット

持分法適用会社には、連結子会社と比較して会計処理の負担が軽減されるというメリットがあります。
持分法適用会社は、連結子会社のようにすべての資産・負債・収益・費用を親会社の財務諸表に統合する必要はありません。
連結子会社の場合、買収先のすべての財務情報を詳細に管理し、財務諸表に統合する必要があるため、膨大なデータの収集と調整作業が発生します。
一方、持分法適用会社であれば、投資先企業の財務情報の詳細な管理は不要であり、純利益の持分相当額を計上するだけで済むため、経理業務の負担が大幅に軽減されます。
また、持分法適用会社の財務状況が急激に変動しても、親会社の財務諸表に与える影響は限定的であり、管理の手間が少なくなる点もメリットです。
そのため、M&A戦略において、フルコントロールを求めない場合には、連結子会社ではなく持分法適用会社として経営に関与することで、財務管理の負担を抑える選択肢が取られることがあります。
持分法適用会社の注意点
持分法を適用させる場合は、以下の注意点についても十分に理解しておかなければなりません。
- 規則に従って確実に注記を記載する
- 自社の判断で終わらせることができない
規則に従って確実に注記を記載する
企業グループ内に持分法適用会社がある場合、連結財務諸表規則に基づいて注記事項に持分法適用会社に関する情報を詳しく記載することが義務付けられています。
具体的には、主に以下の内容を記載しておかなければなりません。
- 持分法を適用した非連結子会社や関連会社の数と、その中で主要な会社の名前
- 持分法を適用しない非連結子会社や関係会社がある場合、その中で主要な会社の名前や持分法を適用しない理由
- 議決権の20~50%を保有しているが関連会社と扱わない場合、当該の会社名と関連会社にしなかった理由
上記の他にもいくつか記載しなければならない注記事項があるため、しっかりと連結財務諸表規則を確認して、正確に記載するように注意しましょう。
自社の判断で終わらせることができない
持分法は、一定の条件を満たす場合に適用が義務付けられる会計処理であり、企業が自由な判断で適用を終了させることができないという点に注意が必要です。
持分法適用の基準は、議決権比率が20~50%であり、かつ経営に重要な影響を与えているかどうかで決まります。
そのため、単に持分法の適用を終了したいという理由だけでは、適用をやめることはできません。
持分法の適用は企業の恣意的な判断ではなく、実態に基づいて決定されるという点に注意しましょう。
持分法の適用を終了させる方法

持分法の適用を終了させる方法としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 保有株式を売却して議決権比率を20%未満に引き下げる
- 株式を追加取得して議決権比率を50%超に引き上げる(連結子会社化する)
持分法は、企業の議決権比率や経営への影響度に基づいて適用が義務付けられる会計処理であるため、企業の判断のみで終了することはできません。
そのため、上記のように持分法が適用される条件を満たさなくなる状況にする必要があります。
持分法の適用を終了させる場合は、財務リスクや経営戦略を考慮しながら適切な方法を選択することが重要です。
経営戦略に基づいて適切に持分法を適用させよう
議決権の20~50%を保有し、経営に重要な影響を与える場合に持分法が適用され、持分法適用会社となります。
連結子会社とは異なり、連結財務諸表には完全に統合されず、会計処理が簡素化できるというメリットがありますが、連結財務諸表規則に基づいて注記事項を正確に記載しなければなりません。
持分法を用いる場合は、持分法適用会社に関する情報を正確に把握したうえで、自社の経営戦略に基づき慎重に判断しましょう。
持分法に疑問や悩みがある場合は、専門家に相談して持分法の適用を検討することをおすすめします。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。