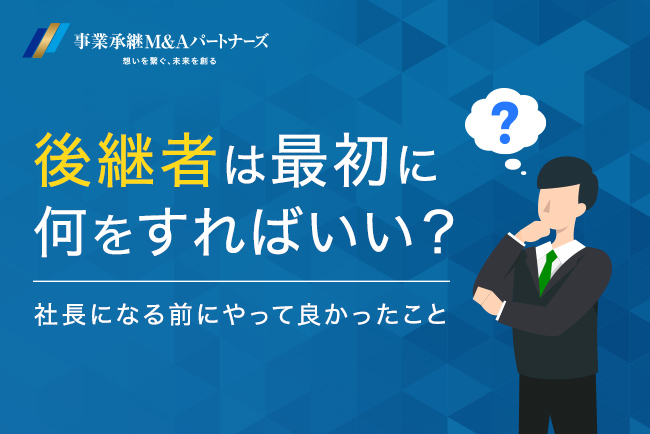遺贈とは、亡くなった方が残した遺言に従い、特定の個人や団体に遺産の一部、あるいは全てを譲ることです。
通常、遺産は相続人しか譲り受ける権利がありませんが、遺言を活用することで、本来は相続権がない個人や団体を受遺者とし、遺産を譲渡することができます。
そして遺贈寄付とは、社会貢献活動に使用することを目的に、特定の個人・団体に遺産を寄付することですが、それによって税金が控除されることがあります。
今回のコラムでは、そんな遺贈寄付について詳しく解説していきます。
遺贈の種類

まずは遺贈の種類から紹介いたします。
包括遺贈
遺産の一部を遺贈するにあたって、「Aさんに財産の〇割、Bさんに〇割を遺贈する」というように、財産の割合を指定して遺贈することを包括遺贈と呼びます。
注意点は、特定の財産を指定するわけではないため、プラスの資産もマイナスの資産も遺贈されるということです。
マイナス資産が多いと、受遺者はその権利を放棄せざるを得なくなる場合があります。
特定遺贈
それに対して、特定遺贈は「Cさんに現金〇〇円を遺贈する」というように、遺贈する財産を具体的に指定します。
遺産の内容をきちんと定めておくことで、不本意にマイナス資産まで引き継がせることがないため、遺贈寄付にはこちらの特定遺贈が推奨されています。
遺贈にかかる税金の種類
遺贈にも税金が課せられます。
以下の3種類があるため、それぞれの内容を解説いたします。
相続税
一つ目は相続税です。
遺贈は贈与と類似する部分があるため、支払義務が発生するのは贈与税だと勘違いされる方が少なくありません。
しかし、遺贈はあくまで被相続人が亡くなってから遺産が譲渡されるため、「遺産を相続した」という認識になり、相続税が課せられます。
不動産取得税
不動産取得税は、その名の通り、売買や贈与によって不動産を取得した際に発生する税金です。
相続や包括遺贈であれば基本的に不動産取得税の課税対象になりませんが、特定遺贈で相続人以外の第三者が不動産を譲り受けた場合は例外です。
例えば「Aさんに不動産を遺贈する」という内容の遺言が残されており、Aさんが相続人ではなかった場合には、不動産取得税が発生します。
登録免許税
不動産に関するもう一つの税金が登録免許税です。
不動産の所有者が変わり、所有権移転登記をする際に課せられる税金ですが、不動産取得税とは違い、受遺者が相続人でも課税対象になり、包括遺贈か特定遺贈かも関係ありません。
ただし、相続人と第三者では税率が異なり、それぞれ以下のように定められています。
- 相続人の場合:固定資産税評価額の1,000分の4
- 第三者の場合:固定資産税評価額の1,000分の20
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を譲り受けた場合、相続人であれば4万円、第三者であれば20万円の登録免許税を納税することになります。
遺贈寄付する方法は?

次に遺贈寄付について解説していきます。
節税効果や注意点について触れていきますが、まずは、遺贈寄付をする方法には、以下の3通りがあるということを理解しておいてください。
遺言による遺贈寄付
遺言書などに、自身の遺産を寄付するという旨を記載しておく方法です。
確実に寄付するためには、どの遺産を寄付するか明確に記載し、誤ってマイナスの資産まで寄付の内容に含めないように注意しましょう。
また、遺贈先の個人・団体に何を寄付するのか事前に伝えておくことが望ましいです。
相続財産による遺贈寄付
被相続人が第三者に直接寄付するのではなく、一旦相続人が遺産を相続し、その後その相続財産を任意の遺贈先に寄付するという方法です。
遺贈先の団体だけでなく、相続人にも寄付する旨を伝えておく必要があります。
生命保険信託による遺贈寄付
生命保険や死亡保険によって得た保険金を寄付するという方法です。
あらかじめ保険金を信託するという契約を保険会社と結んでおくことで、被相続人は任意の団体にそれを寄付することができます。
ただし、寄付できるかどうかは保険会社によるため、活用の意思がある方は事前に確認しておきましょう。
遺贈寄付による節税効果
相続税は本来、遺産総額から基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を差し引いた額が課税対象になりますが、遺贈寄付をした場合は、そこからさらに寄付した金額分を控除することができます。
そして最終的な課税対象額に応じて、相続税が算出されます。
それでは一つ例を挙げ、遺贈寄付を利用することでどれだけの節税効果があるのかをシミュレーションしてみましょう。
条件は以下の通りです。
- 遺産総額:1億円
- 相続人:妻・息子・娘の3人
- 基礎控除額:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
- 遺贈寄与額:2,000万円
遺贈寄付をしない場合
| 妻 | 息子 | 娘 | |
| 遺産総額 | 1億円 | ||
| 基礎控除額 | 4,800万円 | ||
| 遺贈寄付額 | – | ||
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | ||
| 課税対象額(A) |
2,600万円 (5,200万円×1/2) |
1,300万円 (5,200万円×1/4) |
1,300万円 (5,200万円×1/4) |
| 相続税率(B) | 15% | 15% | 15% |
| 控除額(C) | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
| 相続税 (A×B-C) |
340万円 | 145万円 | 145万円 |
遺贈寄付をする場合
| 妻 | 息子 | 娘 | |
| 遺産総額 | 1億円 | ||
| 基礎控除額 | 4,800万円 | ||
| 遺贈寄付額 | 2,000万円 | ||
| 課税遺産総額 | 3,200万円 | ||
| 課税対象額(A) |
1,600万円 (3,200万円×1/2) |
800万円 (3,200万円×1/4) |
800万円 (3,200万円×1/4) |
| 相続税率(B) | 15% | 10% | 10% |
| 控除額(C) | 50万円 | – | – |
| 相続税 (A×B-C) |
190万円 | 80万円 | 80万円 |
二つの表を比較してみると、算出された相続税が、妻は340万円から190万円に、子ども2人は145万円から80万円に、それぞれ節税できていることがわかります。
ただし、2,000万円の遺贈寄付をしているため、最終的に相続人の手元に残る遺産の総額は減少しています。
遺贈寄付をすることで節税することは可能ですが、何も相続できる遺産が増えるわけではないということを理解しておきましょう。
相続税が発生しない遺贈寄付先とは
相続税の控除を受けるためには、遺贈寄付先を必ず寄付金控除が受けられる団体にしなければなりません。
寄付金控除が受けられる団体とは、具体的には以下のような団体を指します。
- 国や地方公共団体
- 認定NPO法人
- 特定公益増進法人
このような団体であれば、寄付した金額分の相続税は控除されるため、節税に繋がります。
しかし、これら以外の団体に寄付しても、基本的には相続税が控除されることはありません。
節税効果を含めて遺贈寄付を検討されている場合は、寄付控除額が受けられるかどうかの確認を怠らないようにしましょう。
遺贈寄付の注意点

最後に、遺贈寄付をする際の注意点を紹介します。
被相続人の意思の通りに寄付できなくなる場合もあるため、一つひとつ確認しておきましょう。
相続人の遺留分を確保する
遺留分とは、遺産において相続人が最低限相続できる取得分のことです。
もし遺贈寄付の額が大きすぎて、遺留分が確保できなくなると、遺贈先の団体は寄付金を手放さなくてはなりません。
場合によっては裁判になる可能性もあるため、遺留分の確保を忘れないようにしましょう。
清算型遺贈が望ましい場合がある
不動産や株式などを現物のまま遺贈する際、その遺産の価値が購入時より上がっていれば、「含み益」が発生します。
その含み益に対する課税を「みなし譲渡課税」と言いますが、包括遺贈である場合を除き、そのみなし譲渡課税は相続人が負担することになります。
つまり、遺産は第三者団体が譲り受けるにも関わらず、税金は相続人が支払わなければならないということです。
そうなるとトラブルにも発展しかねませんが、対処法の一つとして、清算型遺贈があります。
清算型遺贈とは、不動産を現金化し、あらかじめ税金や諸費用を差し引いた額を遺贈するという手法です。
不動産を受け取らない相続人に納税義務が課されることがないため、トラブルを回避することができます。
遺言が無効になる場合がある
遺言書の作成には細かい規定がありますが、もし自筆で作成した遺言書がその規定に反している場合、無効になってしまう可能性があります。
そこで確実に遺贈寄付をする場合には、公正証書遺言がおすすめです。
公証役場で公証人によって作成される公正証書遺言は、法的効力によって無効になることが基本的にないため、最も確実にその効果を発揮することができます。
トラブルを防ぐためにも遺贈寄付は慎重に!
遺贈寄付は社会貢献に繋がるだけでなく節税効果もありますが、実際に行うにはいくつもの注意点があります。
どこかにほころびがあれば、自分の意思通りに遺産を相続・譲渡することができないどころか、相続人や遺贈先の団体にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。
遺産の内容や額、遺贈先によって適切な手法は異なるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。