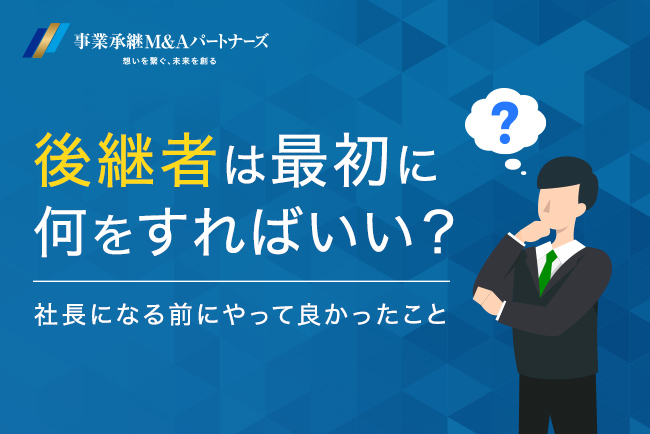事業承継は、主に「親族内承継」「親族外承継」「M&A」の3つの種類に分けられます。
中でも親族内承継は文字通り、親族・血縁関係がある者を後継者として、事業承継する場合のことを指します。
自身の子供や娘婿に事業を承継する場合がありますが、これらは全て親族内承継という事になります。
今回は親族内承継のメリット・デメリットや具体的な手法について詳しく解説いたします。
親族内承継で引き継ぐ3つの要素
親族内承継に関わらず、事業承継をする際は「経営権」「知的資産」「物的資産」の3つの要素を引き継ぐ必要があります。
経営権の承継は文字通り、経営に携わる権利を後継者に引き継ぐことを指します。
知的資産には、前経営者の思いである経営理念や、培ってきた会社のブランドや信用、自社独自のノウハウや技術などが該当します。
他にも前経営者が築いてきた取引先などの人脈も知的資産の一つです。
物的資産としては、自社株式や自社で保有する土地や建物、設備などが該当します。
親族内承継のメリット・デメリット

親族内承継は、親族外承継やM&Aなどとは異なり、身近で気心が知れている親族間で会社を引き継ぐという特徴があります。
それによるメリットは多いですが、一方でデメリットも存在します。
親族内承継のメリット
親族内承継のメリットとしては主に以下の3つが挙げられます。
- 後継者の教育・育成期間が設けやすい
- 後継者が会社内外から受け入れられやすい
- 承継方法の選択肢が多い
後継者の教育・育成期間が設けやすい
後継者候補が早期に決まっている場合、経営者として必要な知識や能力・経験を身につけるための期間を設けやすいというメリットがあります。
育成期間を十分に設けることで、事業承継後に後継者が自信を持って経営をしていくことができるだけでなく、前経営者が会社経営に対して抱く不安も減らすことができます。
前経営者が事業承継後の人生を心置きなく過ごすためにも、後継者の育成期間を確保する重要性は高いと言えます。
多くの場合では、経営者の教育には数年単位の時間が必要となるため、早めの準備を行うようにしましょう。
後継者が会社内外から受け入れられやすい
親族内承継では、前経営者の親族が後継者として会社を引き継ぐため、社内の従業員や役員の納得を得やすく、スムーズに受け入れられる傾向にあります。
また、社外の取引先などにも後継者が受け入れられやすい傾向があります。
中小企業の場合は特に、長年の経営で培ってきた人脈や、取引先との信頼関係は後継者に残したい大きな財産になります。
後継者が前経営者の親族ならば、そのような知的資産を比較的引き継ぎやすくなります。これは、親族内承継のメリットだといえます。
承継方法の選択肢が多い
親族内承継は基本的に「贈与」「譲渡」「相続」といった3つの方法で事業承継されます。
承継の方法によって、手続きや課される税金の種類なども異なります。
親族内承継では、様々な手法が検討できるため、その会社や後継者の置かれている状況に合わせて、最適な方法を選択できます。
親族内承継のデメリット
一方で、親族内承継のデメリットとしては主に以下の3つが挙げられます。
- 親族に必ずしも経営者の資質があるとは限らない
- 親族間でトラブルが発生する可能性がある
- 個人保証の引継ぎ問題が発生する
親族に必ずしも経営者の資質があるとは限らない
会社経営には様々な能力や知識が必要になりますが、親族の中に、必ずしもその適性がある人物がいるとは限りません。
仮に、資質が備わっている後継者候補がいた場合でも、本人に会社を経営する意思がなければ、親族内承継は叶いません。
中小企業の場合は特に、社長の力が会社に与える影響は大きいと言えます。
仮に、後継者に経営能力や経営の意思が無い状態で事業承継を行えば、会社の業績や社内全体の雰囲気に悪影響を及ぼす可能性があります。
親族間でトラブルが発生する可能性がある
親族内承継を行う際は、後継者以外の親族も納得した上で、事業承継するということが大切です。
経営者から後継者への財産の相続が発生する場合には、後継者以外の親族への遺留分を侵害していないか確認しておきましょう。
亡くなった人(被相続人)の相続財産について、特定の法定相続人に最低限保護を与えるための制度です。遺留分は、被相続人の意思に関わらず相続人全員が確保することができるため、事業用資産以外の資産も含めて相続資産がどれくらいあるのかを把握した上で、計画的な遺産分割を行う必要があります。遺留分対策ができていないと、事業を承継しない遺留分権利者に事業用資産が渡ってしまう可能性もあるため、親族内承継を行う場合は遺留分対策についての知識を得ておきましょう。
会社の株式や資産を1人の後継者に贈与することになると、他の親族は不公平さを感じ、相続争いが起こる可能性があります。また、子供に平等な役員のポストと株式を渡し、事業承継を行ったものの、前経営者の死後に会社の経営権を巡って争いが起きたケースもあります。このような結果を招かないためにも、相続人全員が納得した上で事業承継を行えるように、入念な話し合いを行うことが大切です。
個人保証の引継ぎ問題が発生する
会社を経営する上で融資を受けることはごく普通のことであり、それに伴って経営者が個人保証人となっているケースは少なく無いでしょう。
事業承継を行う際に、前経営者の個人保証を外す、もしくは後継者への引継ぎが完了しなければ、完全な事業承継が行えたとは言えません。
しかし、個人保証を引き継ぐ際には以下のような問題が発生する恐れがあります。
- 後継者が個人保証の引継ぎを拒む
- 後継者に個人保証を引き継ぐだけの十分な資力が備わっていない
- 金融機関が個人保証の変更を認めない
親族内承継の基本的な流れ
親族内承継の基本的な流れは下記の通りです。
- 経営状況・課題の把握
- 相続人の指名・意思確認
- 事業承継計画の策定
- 関係者への周知
- 資産の移転と経営の引継ぎ
1. 経営状況・課題の把握
まず、現在の事業や財産の状況を詳細に把握することが重要です。
これには、会社の財務諸表の分析、事業の運営状況の評価を行い、将来のリスクと機会の洗い出しなどをおこないましょう。
事業の強みや弱点、課題や改善すべき点を明確にすることで、後継者が引き継ぎやすい組織・事業へと磨き上げを行っていきます。
※経営課題の洗い出しに関しては、経済産業省が提供しているローカルベンチマークが参考になります。
2. 相続人の指名・意思確認
後継者として適任な家族を特定し、その意思を確認します。
後継者が承継を望んでいるかどうか、経営者としての意欲や適性を確認することが必要です。
複数の相続人候補者がいる場合は、コミュニケーションを通じて家族内の意見調整を図ります。
できるだけ早い段階で意思を確認し、円滑な事業承継に向けた準備を行いましょう。
3. 事業承継計画の策定
次に、事業承継計画を立てます。
これには、後継者の育成やトレーニング、経営権の移譲時期、株式の譲渡や資産の移転の方法、税務計画、事業の継続戦略などが含まれます。
計画を策定する際には、現経営者や後継者の希望や目標を踏まえながら、将来的なリスクに対処する方法も検討します。
事業承継計画を立てることで、後継者や社内、また金融機関に対して計画を共有しやすくなり、説得力も増し、信頼関係維持につながりやすくなります。
※事業承継計画に決まったフォーマットはありませんが、中小企業庁が提供している事業承継計画のフォーマットなどが参考になります。
4. 関係者への周知
事業承継が進む過程で、従業員や取引先、顧客など、関係者に対して周知することが必要です。
適切なタイミングで情報を提供し、関係者の心配や不安を解消するために、コミュニケーションを取りましょう。
5. 資産の移転と経営の引継ぎ
計画が立てられたら、資産の移転と経営の引継ぎを進めます。これには、遺言書の作成、会社の役員や株主の登記の変更、資産の評価と移転手続きなどが含まれます。
後継者に対して、経営者としての責任や役割を理解させるための段階的な移行が重要です。
実際に事業を承継する段階では、税務や法的な手続きにおいては専門家(公認会計士、税理士、弁護士など)の協力を求めることをおすすめします。
親族内承継での具体的な手法
親族内承継では、様々な手法を検討でき、自社の置かれている状況に合わせて最適なプランを選択することができます。
親族内承継で選択できる、様々な手法の中でも、今回は「持株会社の設立」・「事業承継税制の活用」の2つについて解説させていただきます。
持株会社の設立

親族内承継をする際、持株会社を設立するという手法を活用することができます。
持株会社を設立することによって経営の幅が広がり、業績を上げる効果だけでなく、相続税対策も期待できます。
持株会社設立の手順
持株会社を設立する手法を使って事業承継を行う際は、以下の3ステップで行います。
- 会社設立のための資金調達
- 後継者を代表とする持株会社の設立
- 株式の買取りによる、経営権の移行
①会社設立のための資金調達
初めに、後継者が持株会社設立に伴って必要な資金を調達しなければいけません。後継者が十分な資金を保有していない場合では、金融機関からの融資を受けて資金調達をします。
持株会社設立にあたっての融資は、金融機関から認められやすく、比較的容易である傾向があります。
②後継者を代表とする持株会社の設立
十分な資金が確保できた上で、後継者を代表とする持株会社を設立します。
③株式の買取りによる、経営権の移行
持株会社の設立が完了した後に、持株会社の既存会社の株式を全て買い取ります。
これにより実質的には、経営権が持株会社に移行することになり、事業承継が完了します。
持株会社設立における注意点
持株会社の設立が、直ちに相続税の節税に繋がると考える方がいらっしゃいます。
確かに、そのような設立方法もありますが、それが税務署から「相続税の負担を不当に減少させる結果になる」と判断されると、相続税法64条の「同族会社等の行為計算否認規定」に抵触するとして、税務署から認められない場合があります。
税務署から否認された場合、後継者は、本税に加えて加算税、延滞税等の附帯税まで支払わなければいけないことになります。
持株会社の設立による事業承継は、あくまで経営の幅を広げるためや、業績をあげる目的でなければいけません。
その意図が伝わるように、書面に残しておく必要があります。
「同族会社等の行為計算否認規定」に抵触しないように持株会社を設立するためにも、事業承継に詳しい専門家に相談することが望ましいです。
事業承継税制の活用

親族内承継をする際に、事業承継税制を活用することもできます。
事業承継税制を活用することで、後継者に承継された自社株式に対しての相続税や贈与税の納税猶予を受けることができます。
事業承継税制とは
後継者が事業承継を受ける際に、会社の評価額が高ければ、多額の相続税や贈与税を納めなければいけません。
事業承継税制は、そのような事業承継の負担を軽減するために設けられた制度です。
事業承継税制には「一般措置・特例措置」の2種類が存在します。一般措置では、贈与税100%、相続税80%の猶予を受けることができます。
特例措置を利用した場合では、贈与税・相続税どちらでも100%の猶予を受けることが可能です。
特例措置に関しては、2027年の12月31日までという適用期間が設けられているので注意が必要です。
また申請のためには、特例承継計画を提出する必要があり、2024年3月31日2026年3月31日(※)が申請期限となっています。
※提出期限が2年間延長し、2026年3月31日までになりました。
事業承継税制の活用における注意点
事業承継税制は、相続税や贈与税の納税負担を軽減できるため、とても魅力的な制度です。
しかし、納税猶予期間中に取消事由に該当してしまうと、猶予された税額だけでなく、利子税も納付しなければいけなくなるため、注意が必要です。
取消事由に該当するケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 後継者が代表者ではなくなった(身体障害者手帳の交付を受けるなど、やむを得ない場合は除く)
- 資本金又は準備金の額を減少した
- 会社が解散した
- 後継者と同族関係者の議決権の合計が50%以下となった
- 株式が非上場株式ではなくなった
上記の他にも取消事由は20項目以上あります。
事業承継税制を活用するためには、多くの要件や条件を満たす必要があります。
猶予を受けた後も、取消事由に該当しないように長期の間、気を配らなければいけません。
着実に事業承継を行うためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
親族内承継はMACコンサルティンググループにお任せください
MACコンサルティンググループでは、持株会社の設立、事業承継税制の活用、合併、分割、株式交換など、様々な手法を用いて、その会社に合った最適な親族内承継を実現します。
親族内承継でお困りの際はMACコンサルティンググループにご相談ください。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。