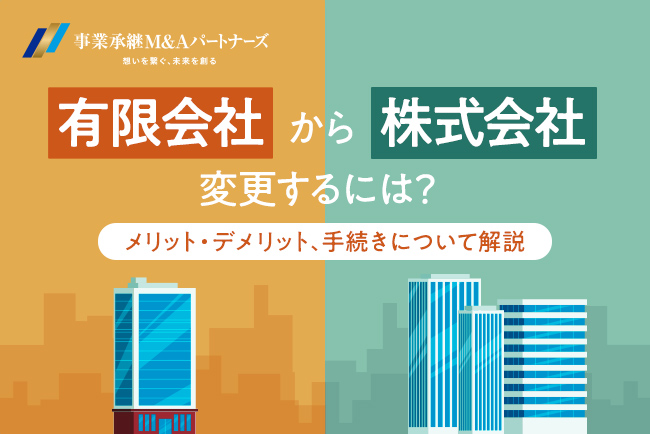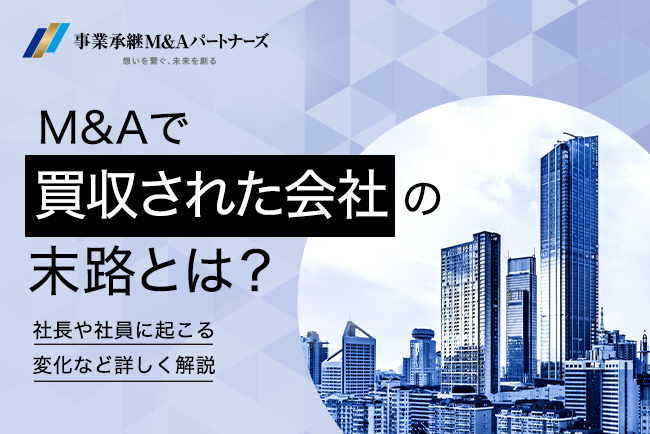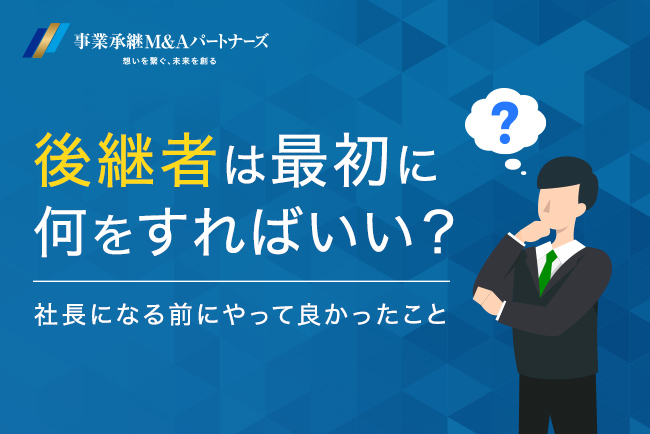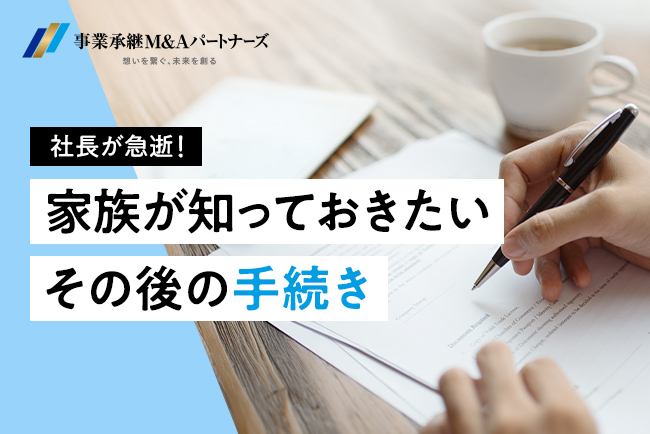事業承継にとって、自社株の相続税は大きな課題となっています。
実際に、後継者が自社株の相続税を支払うことができないということで、事業承継を諦めたりM&Aで会社を売却したりするケースも少なくありません。
そこで、本記事では後継者が自社株の相続税を支払うことができない場合の対処法を詳しく解説します。
また、相続前にできる相続税対策についても解説するので、最後までご覧ください。
自社株の相続税の支払いが難しくなるケース

後継者が自社株の相続税の支払いが難しくなる際のよくあるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 突然の相続で事前準備ができていない
- 自社株以外の資産が多かった
- 自社株の評価額が予想以上に高額だった
突然の相続で事前準備ができていない
突然相続が発生してしまうケースとして最もよくあるケースが、先代経営者の急逝です。
先代経営者が急逝した場合、自社株を相続するための準備が十分に整っていない場合が多く、いきなり相続が発生して相続税が支払えないということが考えられます。
相続の具体的な計画が立てられていない、または計画はあっても十分に進められていないような場合では、高額な相続税を支払える資金を準備できていないことがほとんどでしょう。
自社株以外の財産が多かった
相続税は、自社株の評価額だけで計算するわけではありません。
先代経営者が保有している個人的な財産も含め、死亡時に所有していた全ての財産を基に相続税が計算されます。
相続税対策として、自社株の相続評価額を下げる対策を実施していたとしても、その他の財産が高額だった場合、その効果は十分に発揮されません。
相続税対策を実施する際は、自社株の評価額を下げること以外に、その他の財産に関しても対策をしておくことが重要です。
自社株の評価額が予想以上に高額だった
自社株の評価額は、会社の財務状況や業績、純資産などを基に算出されるため、相続時に会社の売上や利益が大幅に増加している場合、その評価額が急激に上昇するケースが多いです。
また、自社株の評価方法によっては、上場会社の株価に連動して自社株の評価額も高まるケースもあります。(類似業種比準方式)
こうした急激な評価額の上昇は、事前の計画では想定されていない場合が多く、結果として相続税が高額になり、後継者が納税資金を確保できなくなるリスクを生じさせます。
このような事態を防ぐためには、定期的に自社株の評価額を見直し、事前に事業承継税制や納税猶予の制度を活用するなどの対策を講じることが重要です。
後継者が自社株の相続税を支払えない場合の対処法

相続が発生した際に、後継者が自社株の相続税を支払えない場合の対処法を解説します。
主に以下の5つの対処法があります。
- 会社が自社株を買い取る(金庫株)
- 個人資産を売却する
- 延納・物納制度を利用する
- 自社株を他社に売却する(M&A)
- 相続を放棄する
会社が自社株を買い取る(金庫株)
後継者が自社株の相続税を支払えない場合、会社が自社株を買い取る「金庫株」の活用は有効な対処法の一つです。
金庫株とは、会社自身が自社株を買い取って、保有する株式のことを指します。
金庫株を活用すると、会社が後継者から株式を買い取ることで、後継者は相続税の支払いに必要な現金を確保することが可能です。
一方で、金庫株を活用するためには、会社が買取り資金を用意できることが条件です。
また、金庫株は配当を生まないため、会社の資本効率に影響を与える可能性があります。
さらに、金庫株取得は会社法の規定に従い、株主総会の特別決議を必要とする場合があるため、株主が複数存在する場合は事前準備が重要です。
個人資産を売却する
先代経営者の個人資産を売却することで、納税に必要な資金を準備することができる可能性があります。
相続税は先代経営者が所有する全ての財産を対象に計算されるため、現金で支払えない場合、資産の現金化が資金を確保する方法として役立ちます。
例えば、不動産、預貯金、有価証券、車両、骨董品、貴金属などの個人資産を売却し、その売却益を相続税の納税資金として充当することが可能です。
特に、評価額が高いものの現金化が容易な資産(例:不動産や上場株式)は、短期間で納税資金を準備する手段として適しています。
ただし、資産の売却に伴い譲渡所得税が発生する場合があるという点に注意が必要です。
また、短期間で売却を進めると本来の資産評価額より低い価格で手放してしまうリスクもあります。
延納・物納制度を利用する
相続税は原則として、現金一括で支払う必要があります。
しかし、相続税が高額で資金を準備することができない場合、相続税の延納・物納制度を活用することが可能です。
延納とは、相続税を分割払いにして最長20年まで納税期間を延長できる制度です。
この制度を利用することで、毎年の現金負担を軽減し、納税資金を計画的に準備できるようになります。
自社株の相続税の場合は担保の提供が必要になりますが、一般的には相続した自社株や不動産が担保として認められます。
延納には利子税(延納利率)がかかりますが、無理のない納税スケジュールを立てることができるようになるでしょう。
物納とは、現金で相続税を支払うことが困難な場合に、相続した財産を納税に充てる制度です。
自社株や不動産などの物納が認められれば、現金納付が不要になります。
物納は、延納を利用してもなお納税が困難な場合に限り認められ、厳しい条件があります。
特に自社株については、財務状況が健全で譲渡可能な状態でなければ認められないでしょう。
延納・物納制度には、厳しい条件があったり手続きに時間がかかったりするため、早めに制度の活用を検討して、準備を進めておく必要があります。
これらの制度を利用すると、総納税額が増える可能性はありますが、資金確保が難しい場合でも会社や後継者のキャッシュフローを守りながら事業承継を進めることが可能です。
自社株を他社に売却する(M&A)
後継者が自社株の相続税を支払えない場合、M&Aで自社株を他社に売却することも一つの選択肢です。
自社株を他社に売却することで、相続税を支払うための現金を確保できるだけでなく、事業を存続させながら、経営のバトンタッチを実現することが可能です。
M&Aでは、自社の事業に共感し、長期的な成長を目指す買い手企業を選ぶことで、従業員の雇用や取引先との関係を維持することもできます。
ただし、M&Aを進める際には、会社が持つ価値を適切に評価し、信頼できる買い手を見つけることが重要です。
相続を放棄する
後継者が自社株の相続税を支払えない場合、最終手段として相続を放棄するという選択肢もあります。
これにより、財産の相続を放棄することになるので相続税も発生しません。
ただし、相続放棄をすると、自社株を含む全ての相続財産を受け取る権利が失われるため、会社の経営権も放棄することになります。
次順位の相続人が株式を相続するか、全相続人が放棄した場合は「相続財産管理人」が株式を管理することになり、最終的に会社が清算や売却されるでしょう。
相続放棄は、先代経営者の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄をすると相続税の支払いをする必要はなくなりますが、事業承継を断念する結果にもなるため、慎重な判断が求められます。
後継者の負担を減らすための相続税対策

後継者の相続税の負担を減らすためには、相続が発生する前に対策を講じておくことが重要です。
会社や個人の状況に合わせて適切な対策を講じ、相続税がしっかり支払えるように準備をしておきましょう。
- 事業承継税制を活用する
- 自社株の評価額の上昇を抑える
- 生命保険を活用する
- 生前贈与を行う
事業承継税制を活用する
相続税対策として真っ先に検討するべき方法が、事業承継税制の活用です。
事業承継税制とは、一定の条件を満たせば、相続税や贈与税の納税を猶予し、最終的に免除される制度で、中小企業の事業承継を円滑に進めることを目的としています。
具体的には、後継者が会社の代表者に就任し、事業を継続することを条件に、自社株の評価額に基づく相続税や贈与税の納税が猶予されます。
また、一定期間後に事業継続要件を満たしていれば、納税額が免除される仕組みです。
事業承継税制を活用すれば、納税資金を確保する負担を大幅に軽減でき、会社のキャッシュフローを保ちながら事業承継が可能になります。
ただし、制度の適用には細かい条件があり、事前の計画と手続きが必要です。
専門家の助言を受け、必要な準備を進めることで、効果的に相続税負担を減らし、スムーズな事業承継を実現できます。
事業承継税制についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、詳細が気になる方はこちらの記事をご覧ください。
事業承継税制とは?贈与税・相続税の納税猶予や免除要件をわかりやすく解説
事業承継税制とは、事業承継に関する贈与税・相続税を猶予される制度です。後継者の死亡などにより最終的には免除とな…
自社株の評価額の上昇を抑える
後継者の相続税の負担を減らすために、自社株の評価額の上昇を抑えることは非常に有効な対策です。
相続税は、自社株の評価額を基に計算されるため、評価額が高くなるほど相続税も増加します。
そのため、事前に株式の評価額を適切に抑えることで、相続税の負担を軽減することができます。
自社株の評価額は、会社の純資産額や収益性を基に算出されるため、これらを調整することがポイントです。
具体的には、以下の方法が挙げられます。
- 役員報酬の引上げ
- 役員退職金の支給
- 含み損のある不動産の売却
- 配当金の抑制
- 持株会社化による高収益部門の分離
上記の対策を講じることで、会社の利益を圧縮したり純資産額を抑えたりすることができるため、必要以上に自社株の評価額が上昇しないように抑制することが可能です。
ただし、不自然な資産操作や利益調整は税務当局から否認される可能性があるため、法令に基づいて慎重に行う必要があります。
生命保険を活用する
先代経営者が生命保険に加入し、後継者を保険金の受取人に設定することで、相続税の納税資金を確保することができます。
生命保険金は相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になるため、一定額までは課税負担を抑えつつ現金を受け取ることが可能です。
相続税の納税には現金が必要なため、生命保険金を受け取ることで納税資金に充てることができます。
さらに、生命保険金は他の相続財産と異なり、遺産分割協議を経ずに受取人が指定された額を直接受け取れるため、後継者がスムーズに納税に利用できる点もメリットです。
生前贈与を行う
生前贈与を活用することで、相続財産そのものを事前に減らし、相続税の課税対象額を引き下げることが可能です。
通常、生前贈与にも贈与税が課せられ、相続税よりも税率が高く設定されているので税負担が高額になります。
しかし、生前贈与には暦年贈与という仕組みがあり、暦年贈与をすることで年間110万円まで非課税で財産を贈与できる「贈与税の基礎控除」を活用することが可能です。
暦年贈与を複数年にわたって継続的に行えば、大きな財産でも時間をかけて課税対象を減らすことができます。
相続税対策を講じて後継者の負担を減らしましょう
何も対策をしていなければ、自社株の相続税は高額になり後継者に大きな負担をかけてしまいます。
高額な相続税が原因で、事業承継が困難になったり、会社を存続させることが難しくなったりしてしまう可能性が考えられるため、事前に適切な対策を講じておきましょう。
自社株の相続税対策を進める際は、早めの準備が非常に重要です。
いずれの対策も一朝一夕では効果が得られないため、しっかりと時間をかけて計画的に進めていきましょう。
MACコンサルティンググループでは、親族内承継に精通した事業承継コンサルタントが、経営者や後継者、会社の状況に合わせて最適な事業承継プランをご提案します。
有効な自社株対策や事業承継税制の活用もサポートしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。