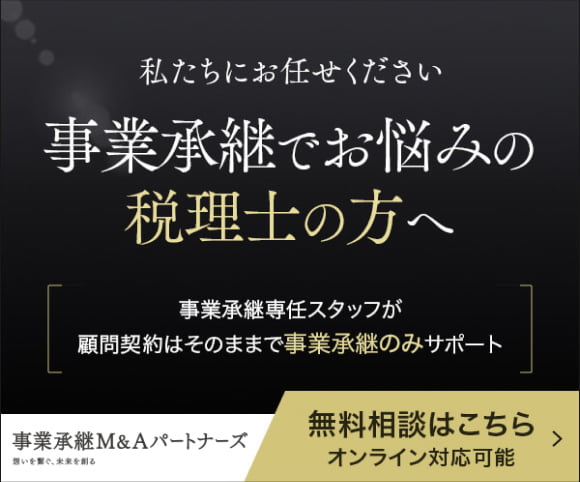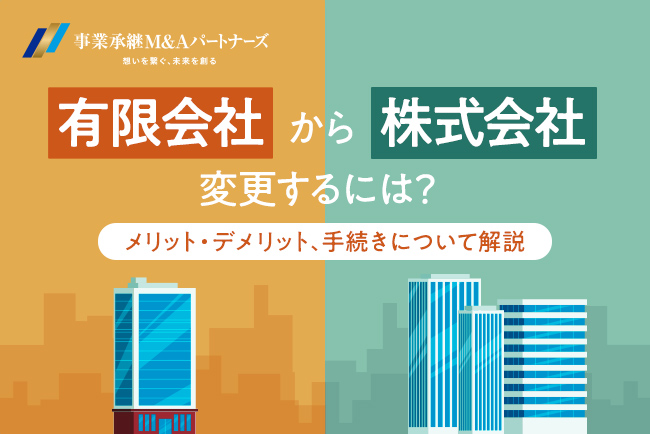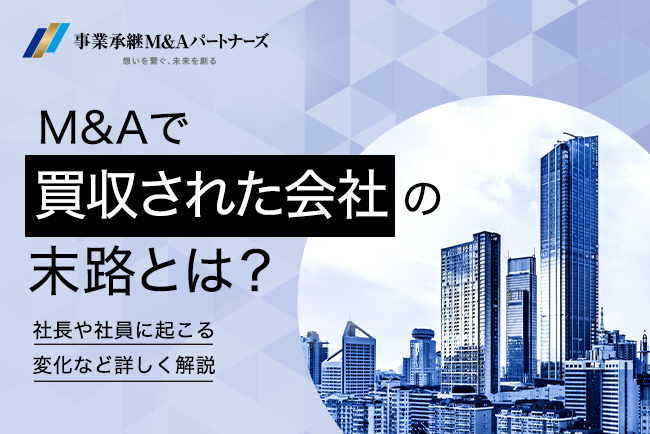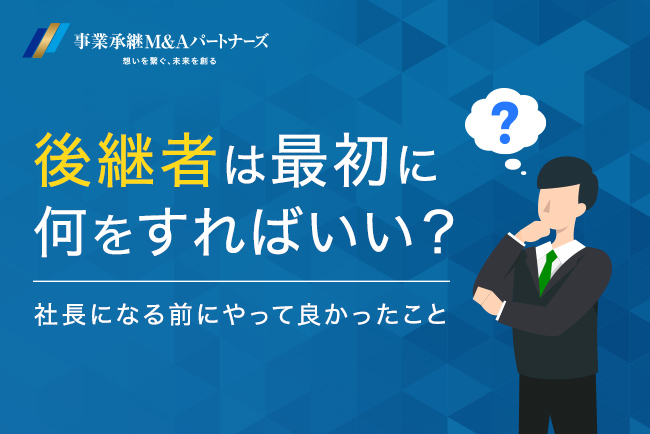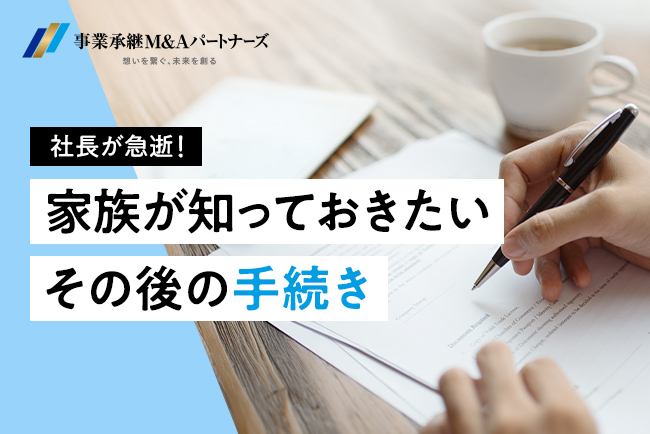事業承継税制とは、事業承継に関する贈与税・相続税を猶予される制度です。後継者の死亡などにより最終的には免除となります。
平成30年度の税制改正で、これまでの措置に加え10年間の時限的措置として要件を大きく拡充した新制度が創設されました。
国税庁のWebサイトではこの時限的措置を「特例措置」、通常の事業承継税制を「一般措置」と区分しています。
今回は特例措置を中心に、事業承継税制をわかりやすく解説していきます。
事業承継問題の深刻化が背景「特例事業承継税制」
 我が国において、地域経済や雇用を支えている中小企業は国内経済の大きな柱です。
我が国において、地域経済や雇用を支えている中小企業は国内経済の大きな柱です。
しかし、中小企業の後継者不足は深刻化しており「廃業」を選択する中小企業の経営者は少なくありません。
現在、多くの経営者が事業承継の計画が進まず、見込みが立たないまま高齢となり、引退年齢を迎えています。
事業承継の後継者不足は、こちらの記事でも詳細にお伝えしています。
後継者難倒産とは?後継者不在に悩む経営者が知るべき現状と解決策
現在の日本には、次世代の会社の担い手となる後継者が不足しており、廃業を余儀なくされる企業が多く存在します。なぜ…
事業承継の最大ハードルは自社株の後継者への承継です。
株式譲渡に係る贈与税・相続税の負担は重く、事業承継を行う際の大きな壁になります。
このハードルを下げ、中小企業の事業承継を推進するために平成21年に制定されたのが事業承継税制です。
ですが、事業承継税制の要件は厳格なため活用例が少ないこともあり、はじまってから改正が重ねられてきました。
そして平成30年に時限的な措置として創設されたのが、冒頭でも解説した特例措置です。
特例措置と一般措置は同時に存続
一般措置は、恒久措置として特例措置と同時に存続しています。
事業承継税制を利用する際は特例措置を選択し、特例措置を使えるように準備を進めなくてはいけません。
利用するための申請期間にも限りがあるため、漏れのないように確認していきましょう。
特例措置はいつからいつまで?
申請期間
特例措置の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日令和8年3月31日までに、特例承継計画の提出が必要です。
この特例承継計画の提出が、事業承継税制の特例措置を利用するスタートになります。
※特例承継計画の提出期間は令和6年3月31日までとされていましたが、令和5年度税制改正大綱にて、2年延長されることが決定しました。詳しくは下記記事をご覧ください。
事業承継税制の特例承継計画提出期限の延長が決定!いつまで?注意点や提出の流れも解説
事業承継M&Aパートナーズでは、特例承継計画の作成・提出のご支援が可能です。グループスタッフ200名以…
対象・適応期間
平成30年4月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続が条件となります。
事業承継税制「特例措置」と「一般措置」の違いとは?
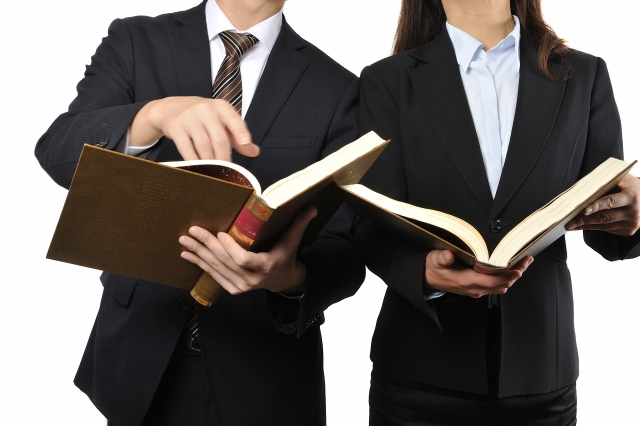
| 一般処置 | 特例処置 | |
| 対象株数 | 総株式数の最大3分の2まで | 全株式 |
| 納税猶予割合 | 贈与:100% 相続:80% |
贈与:100% 相続:100% |
| 承継パターン | 複数の株主から 1人の後継者 |
複数の株主が 最大3人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
緩和 |
猶予の対象株式2/3から全株式に
一般措置では、猶予となる対象株式は2/3まででした。
しかし、特例措置では全株が対象なります。
納税猶予割合「贈与税」「相続税」いずれも100%に
納税猶予の割合が、贈与税100%、相続税80%だったものが、今回の特例措置ではいずれも100%猶予対象となります。
ポイント
承継パターンは複数の株主から3名まで適応可能
後継者の対象も拡充されています。
一般措置では後継者は1人まででしたが、特例措置では最大3人まで対象となっています。
複数の後継者に適用する場合、後継者全員を代表者にする必要があります。
相続時精算課税が直系卑属外でも使える
元々、相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子ども、もしくは孫への贈与が2,500万円まで猶予され、相続時に贈与分が相続財産と合算、相続税として課税される制度です。
今回の特例措置では、従業員や第三者などの直系卑属以外の後継者でも相続時精算課税制度の適用が認められました。
雇用確保に関する要件のハードルが下がった
事業承継税制の要件の中で、最も厳格と言われ、ハードルが高いとされているのが雇用確保です。
一般措置では5年間で平均8割の雇用確保維持が絶対条件でした。
しかし、特例措置では、平均8割を下回っても、業績悪化などの正当な理由があれば、納税猶予を継続できるようになっています。
理由を記載した書面を提出し、認定経営革新等支援機関から指導を受けることを条件として、猶予が継続されます。
承継後の廃業時のリスクが軽減された
事業承継から5年経過後、会社を解散した場合は全額納税の義務が課せられますが、特例措置では猶予されていた納税額の一部が免除されます。
事業承継税制における納税免除の要件は?
事業承継税制において、納税が猶予から免除になる主なタイミングは以下の4つになります。
- 先代経営者が死亡したとき
- 後継者が死亡したとき
- 申告期限から5年以上経過した後に、会社が破産手続き開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき
- 次の後継者に事業承継が行われたとき
他にも特例で納税が免除になったり、贈与税・相続税の一部が免除になる可能性もあります。
特例事業承継税制を利用するための【会社】の要件
経営承継円滑化法に規定する中小企業であること
経営承継円滑化法が定める中小企業は、以下の通りです。
経営承継円滑化法に定める中小企業の基準
| 業種 | どちらからを満たす(資本金・従業員) | |
| 資本金 | 従業員数 | |
| 製造業・その他業種(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(※1)卸売業、小売業、サービス業を除く。
(※2)自動車または航空機タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
上場企業でないこと
上場企業は事業承継税制を利用できません。
風俗営業会社でないこと
ゲームセンターやパチンコ店などは、事業を営むうえで風俗営業許可が必要ですが、事業承継税制の適用は認められます。
しかし、性風俗営業会社は事業承継税制の適用は認められません。
資産管理会社に該当しないこと
資産管理会社とは、「有価証券・自社で利用していない不動産・現預金等の特定資産の保有割合が70%以上の会社のこと」、または、「これらの特例資産からの運用収入が総収入の75%以上の会社のこと」を指します。
資産管理会社であっても、以下の条件をすべて満たせば特例事業承継税制の適用が可能です。
- 従業員が5名以上
- 事務所を所有している、もしくは借りている
- 商品やサービスの販売を3年以上行っている
特例事業承継税制を利用するための【先代経営者】の要件
- 会社の代表者であったこと(過去に代表者の時期があれば、贈与直前に代表権がなくても適用可能)
- 贈与直前に、贈与者および親族などで発行済み株式数(総議決権数)の50%超を所有し、かつ、親族などの中で後継者を除いて最も多くの株式を保有していること
- 贈与時、代表権を有していないこと (贈与ではなく、相続だった場合、死亡時に代表者であっても適用が可能)
特例事業承継税制を利用するための【贈与者(先代経営者以外)】の要件
- 会社の代表権を有していないこと(相続だった場合は、代表者であっても適用が可能)
- 先代経営者の贈与後に、贈与を行うこと
- 一定数以上の株式を贈与すること
- 特例措置の適用を受ける贈与をしていないこと
特例事業承継税制を利用するための【後継者】の要件
- 贈与時に後継者を含めた同族関係者で発行済み株式の50%超を所有していること
- 贈与時に同族関係者の中で後継者が最も多く株式を保有していること(後継者が複数の場合、全員が発行済み株式の10%を保有しているかつ、後継者全員が最も多く株式を保有していること)
- 贈与時に18歳以上であること(相続の場合、18歳未満でも適用が可能)
- 贈与時に役員就任から3年以上経過していること(相続の場合、相続開始時に役員であれば適用が可能)
- 贈与時に代表権を有していること(相続の場合は、相続開始の翌日から5か月以内に代表者に就任することが条件)
後継者の要件は、他の要件よりも複雑になっているため、理解が難しいかもしれません。
事業承継税制の後継者に関する要件をわかりやすくまとめたコラムがあるので、参考にしてください。
事業承継税制の後継者要件を正しく把握!特例措置を受けるためには
特例承継計画の提出期限が2024年(令和6年)3月31日2026年(令和8年)3月31日に迫り、特に注目が高ま…
事業承継税制の適用は取り消される場合がある
 事業承継税制は、1度適用を受ければその効力がずっと続くわけではないという点に注意しなければいけません。
事業承継税制は、1度適用を受ければその効力がずっと続くわけではないという点に注意しなければいけません。
事業承継税制が適用された後も、一定の条件を満たしていなければ納税猶予が認められなくなり、後継者は即時多額の税金を納めることになります。
事業承継後5年間だけ適用される取消事由と、6年目以降に適用される取消事由は異なるため注意しましょう。
それぞれをまとめると以下のようになります。
事業承継後5年間だけ適用される取消事由
- 後継者が代表者ではなくなった
- 平均従業員数が8割を下回った
- 都道府県・税務署への届出を提出しなかった
- 後継者と同族関係者の議決権が5割を下回った
- 後継者以外の同族関係者が後継者の議決権を超えた
- 会社が解散または組織変更をした
- 納税猶予対象株式を一部または全部譲渡した
- 黄金株を後継者以外の者が保有した
事業承継後6年目以降に適用される取消事由
- 税務署へ継続届出書を提出しなかった
- 納税猶予対象株式の一部または全部譲渡した
- 資産管理会社に該当した
- 本業の収入が無くなった
取消事由に関して詳しく解説した記事があるので、理解を深めたい方はこちらのコラムをご覧ください。
【事業承継税制】取消事由をわかりやすく解説!リスクやポイントも紹介
事業承継の際に発生する多額の税負担から、事業承継を躊躇する経営者や後継者が多く、実施に踏み出せない企業も少なく…
事業承継M&Aパートナーズにご相談ください
事業承継M&Aパートナーズは、20名以上のコンサルタント、グループ会社総勢約200名のスタッフから成る、事業承継のスペシャリスト集団です。
- フルオーダーメイド事業承継
- 各士業の専門家によるワンストップサービス
- 事業承継のセミナー実績多数
- 幅広い年代のスタッフ
このような強みがあり、多くのお客様にご愛顧いただいております。
どのような些細なお悩みでも、専門家が丁寧に対応させていただくので、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。