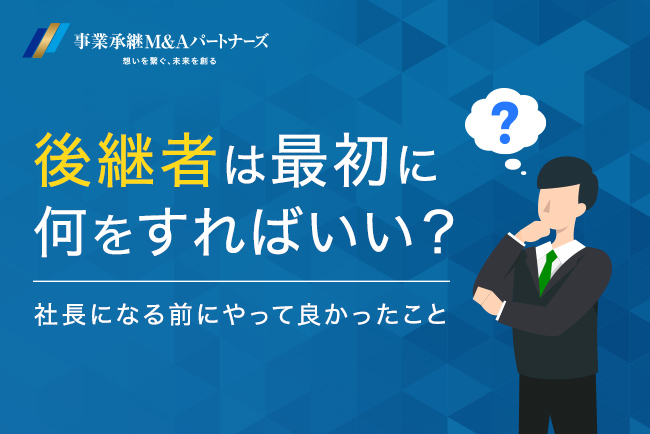遺留分とは、一定の相続人に最低限取得できる財産を保証される遺産取得分のことです。
例えば、被相続人が遺産の全てを長男に相続させるという内容の遺言を残していた場合、そのままだと他の相続人は一切の遺産を相続することができませんが、遺留分を主張することで、一定割合の遺産を取得することができます。
このように、遺留分は遺言の内容より優先されるほど強い効力を持ちますが、その額はどれほどになるのでしょうか。
また、場合によっては遺留分を減らしたいというケースも発生しますが、具体的にはどのような対策をとればよいのでしょうか。
これらの疑問を解消するため、今回のコラムでは遺留分の計算方法や、遺留分対策について解説いたします。
法定相続分と遺留分の割合

まずは法定相続分と遺留分の割合を確認しましょう。
法定相続分とは、民法によって定められた、各相続人が取得できる遺産の取り分です。
遺言が残されておらず、相続人全員によって遺産分割協議が行われた際には、この法定相続分に従って遺産が分配されることが一般的です。
遺留分の計算にはこの法定相続分も関係しますが、基本的な相続人の組み合わせにおける、それぞれの法定相続分と遺留分は以下の通りです。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 全て | 1/2 |
| 子どものみ | 全て | 1/2 |
| 父母のみ | 全て | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 全て | なし |
| 配偶者と子ども | 配偶者:1/2 子ども:1/2 |
配偶者:1/4 子ども:1/4 |
| 配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3 |
配偶者:1/3 父母:1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
実際に法定相続分・遺留分を計算する際に注意すべき点は、同じ相続順位の相続人が複数人いる場合は、それぞれの割合を等分する必要があるということです。
例えば、相続人が配偶者と子ども3人である場合、子どもの法定相続分は1/2と表にありますが、それを3人で等分しなければならないため、1人当たりの法定相続分は1/6になります。
遺留分も同様に等分する必要があり、1人当たりの遺留分は1/12になります。
遺留分の計算方法

それでは具体的に遺留分がいくらになるのか、例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
配偶者・子ども2人がいる場合
仮に配偶者と子どもがいる場合、先ほどの表に従うと、それぞれの遺留分は総額の1/4になります。
しかし、今回は子どもが2人いるため、1/4をさらに2等分し、子ども1人当たりの遺留分は1/8ということになります。
遺産総額が1,000万円だとすると、配偶者は1/4の250万円、子ども1人当たりは1/8の125万円が、遺留分として最低限取得できる財産ということになります。
配偶者・父母がいる場合
次に子どもがおらず、配偶者と父母がいる場合、再び表から算出すると、配偶者は1/3で、父母は1/6が遺留分として保証されています。
ただし、父母はその1/6の遺留分を2人で等分することになるため、1/12が1人当たりの遺留分になります。
遺産総額が1,200万円だとすると、配偶者は400万円、父母はそれぞれ100万円の財産を取得することが保証されます。
基礎財産の計算方法の注意点
遺留分は遺産総額を示す「基礎財産」を対象に算出されますが、この基礎財産は被相続人が保有していた財産だけを指すわけではありません。
それぞれのケースに応じて、以下のような項目を加算、あるいは減算する必要があります。
生前贈与がある場合
亡くなる前に、個人から別の個人へ財産を贈与することを生前贈与と呼びます。
節税を目的によく行われますが、死亡前の1年間(相続人に対する贈与の場合は10年間)に渡って贈与された財産の分は、基礎財産に加算されます。
また、その生前贈与によって遺留分を持つ相続人に損害を与えるということをわかっていた場合は、1年(10年)以上前に贈与された分も加算することになります。
売却された財産がある場合
被相続人が不相当な対価で財産を売却し、その行為によって相続人の遺留分が侵害されることをわかっていた場合は、その分も基礎財産に加算されます。
積極財産がある場合
株式・有価証券・不動産など、現金以外にも様々な形の財産がありますが、それらは積極財産と呼ばれ、基礎財産に加算されます。
ただし、それらの価値は具体的に数値化されているわけではないため、そのままだと計算することができません。
まずはそれぞれの積極財産の評価額を算出し、可視化するステップを踏む必要があります。
被相続人に債務があった場合
被相続人は借金や債務を負っている場合があります。
その分の額は基礎財産から差し引いて計算することができますが、返済義務はそのまま相続人へ移ることになります。
生前にできる遺留分対策

遺留分を意図的に減額することを遺留分対策と呼びますが、そのような対策が必要となる例を一つ挙げましょう。
両親と子どもの3人家族があったとして、母親の浮気が原因で家族は別居、子どもは父親が育てることになり、お互いほとんど連絡も取らないほど疎遠になってしまったとします。
仮にこのような家庭においても、父親が亡くなってしまった場合には、母親は遺留分として最低でも相続財産の1/4を請求できる権利を持っていますが、父親は可能な限り多くの遺産を子どもに相続してほしいと考えています。
そこで遺留分対策が必要になります。
あらかじめ遺留分を減らすための対策をとっておくことで、不本意な相続人に対する相続分を減らすことができます。
相続権を放棄するよう説得する
最も穏便に済ますことができる可能性があるのは、相続権を放棄するよう説得することです。
生前に直接伝える、遺言書にその旨を記載するなど、説得する手段に特に決まりはありませんが、それによって納得してもらうことができれば、本当に相続したい人にだけ、遺産を残すことができます。
ただ、いずれの手段で説得したとしても、それだけでは法的な効力がありません。
家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをすることで遺留分を放棄させることも可能ですが、それには遺留分を放棄する相続人本人が申立てをしなければならず、後の撤回も可能なため、確実な方法とはいえません。
相続したくない!相続放棄のメリット・デメリットや手続きを解説!
被相続人が残した財産の相続権を放棄することを「相続放棄」と言います。現金や不動産といったプラスの財産だけでなく…
生命保険を活用する
生命保険の保険金請求権は、相続財産には含まれず、あくまで保険金受取人の固有財産です。
つまり、被相続人が生命保険に加入し、受取人に任意の相続人を指定しておけば、結果としてその相続人に対して、多めに財産を残すことができます。
経営承継円滑化法を活用する
被相続人が企業の代表者である場合、その遺産総額は非常に大きくなってしまう場合が多いです。
そのまま相続をすると遺留分も大きくなり過ぎてしまいますが、会社の株式を生前贈与しても、遺留分侵害とみなされてしまうでしょう。
そのような場合には、経営承継円滑化法を活用することができます。
経営承継円滑化法には以下の特例制度が設けられており、遺留分対策として機能する場合があります。
除外合意
除外合意は、相続人全員の合意を得ることによって、会社の株式を基礎財産から除外することです。
大きな価値を持つ株式が遺留分の対象外となることで、遺留分の額は大きく下がります。
固定合意
相続人全員が合意した時点で株式の評価額を固定し、基礎財産に含めておくことを固定合意と呼びます。
評価額を固定してから被相続人が亡くなるまでの間、実際の自社株式の金額がどれだけ高くなろうと財産としての価値は固定されているため、後継者の経営努力の一部を他の相続人に横取りされるということを防ぐことができます。
付随合意
付随合意は、後継者も含めた相続人全員が被相続人から贈与された財産を遺留分の対象外とすることです。
会社の株式以外にも、不動産や現金といった財産が既に贈与されている場合、それらを遺留分の対象外とすることで、さらに金額を下げることができます。
上記した除外合意や固定合意と併せて活用されます。
仕組みを理解して遺留分を調節しよう!
今回のコラムでは、遺留分の計算方法や、その割合を下げるための遺留分対策について解説いたしました。
遺留分は、相続人が取得できる財産を守るためにも欠かすことができない制度ですが、場合によっては悪い方向に効果を発揮してしまうことも考えられます。
必要に応じて遺留分対策をとり、望まない相続にならないよう、今のうちから準備を進めましょう。
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。